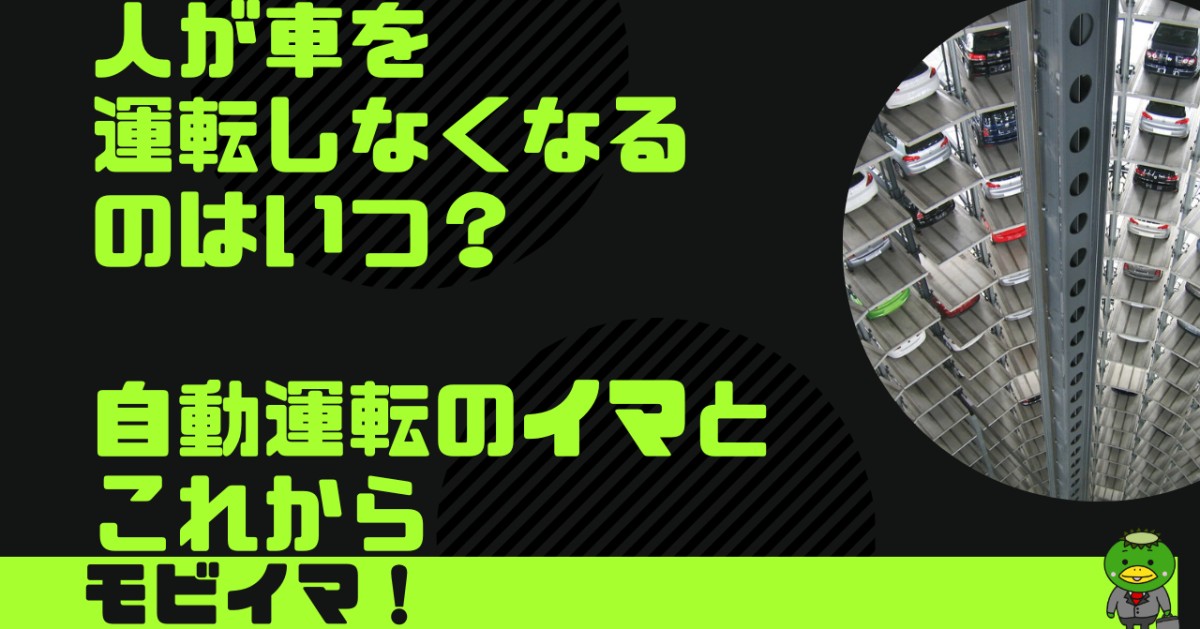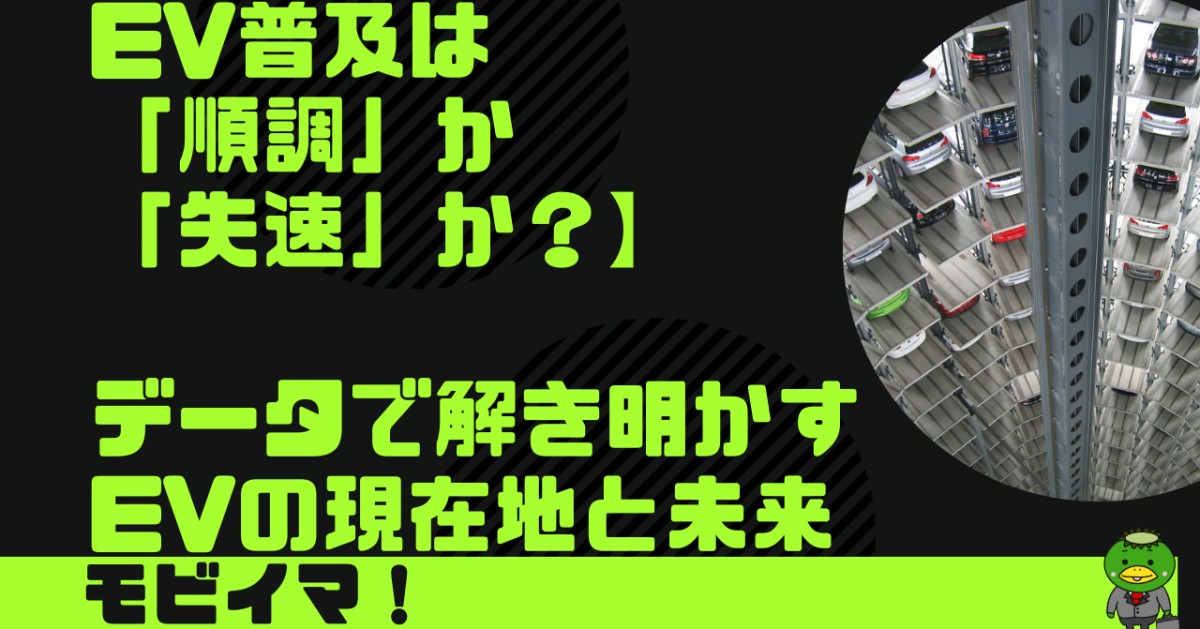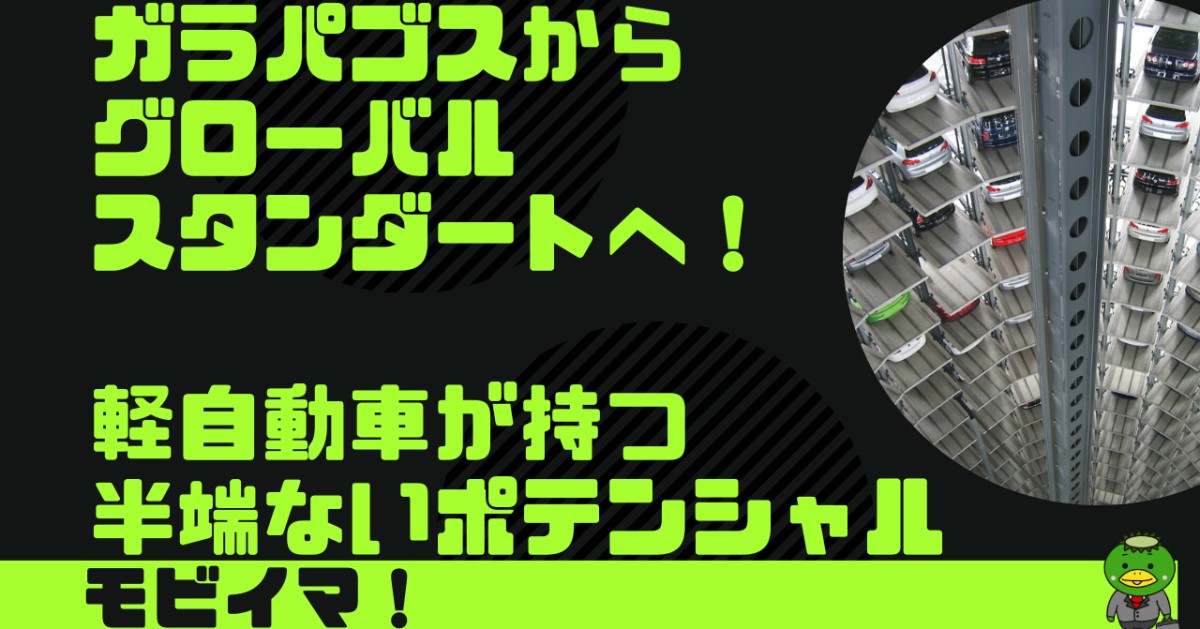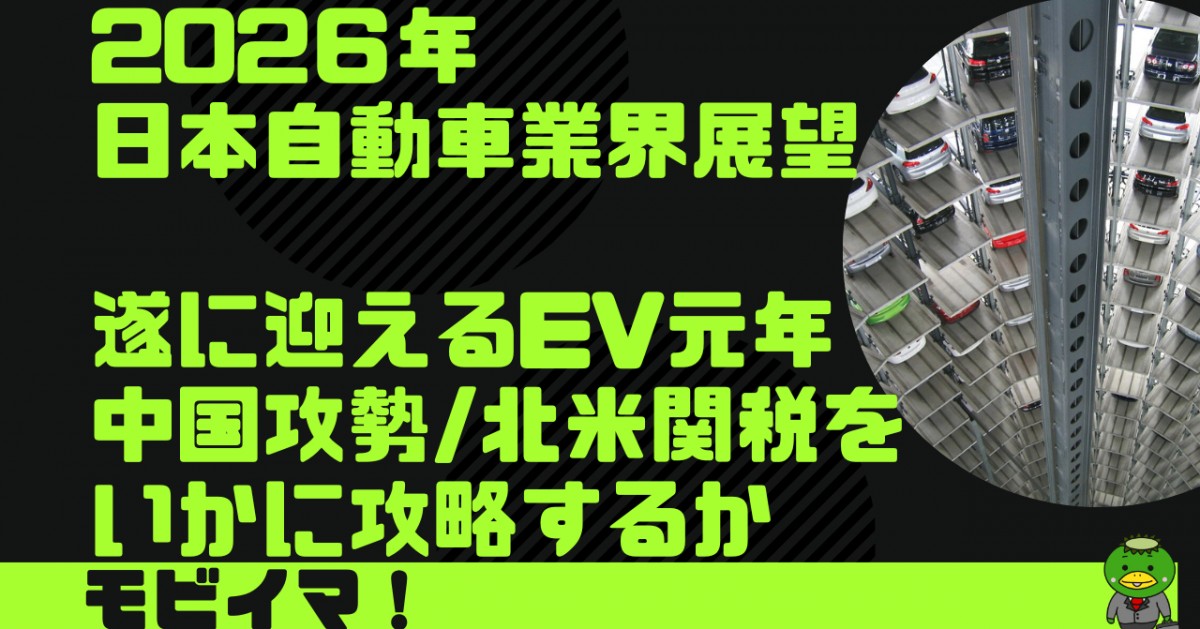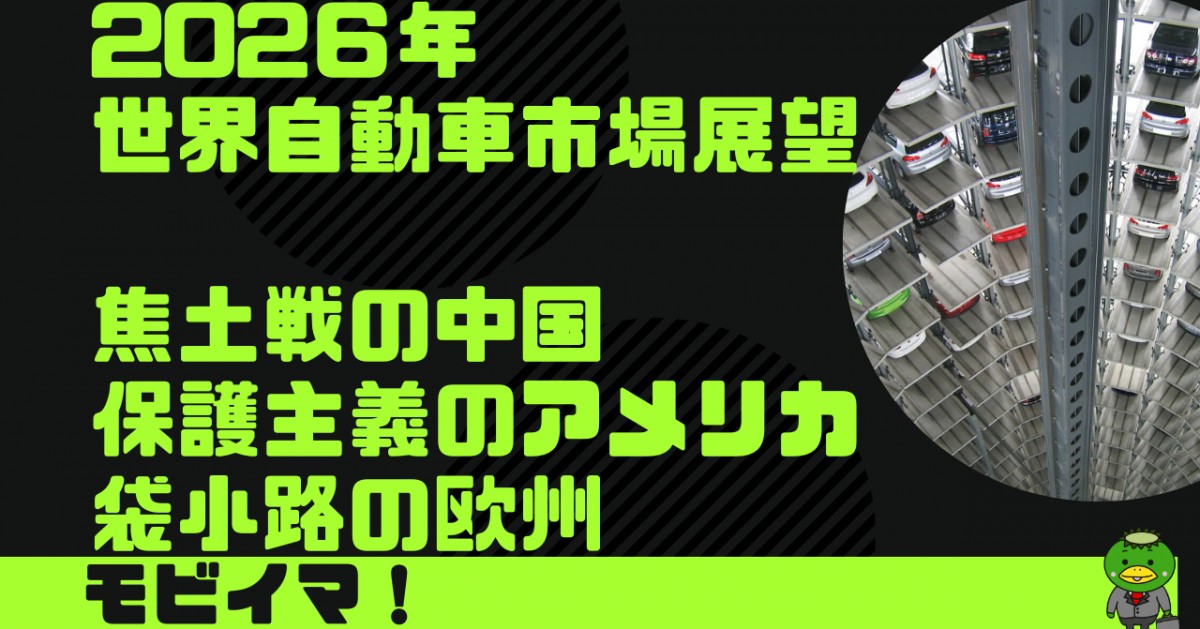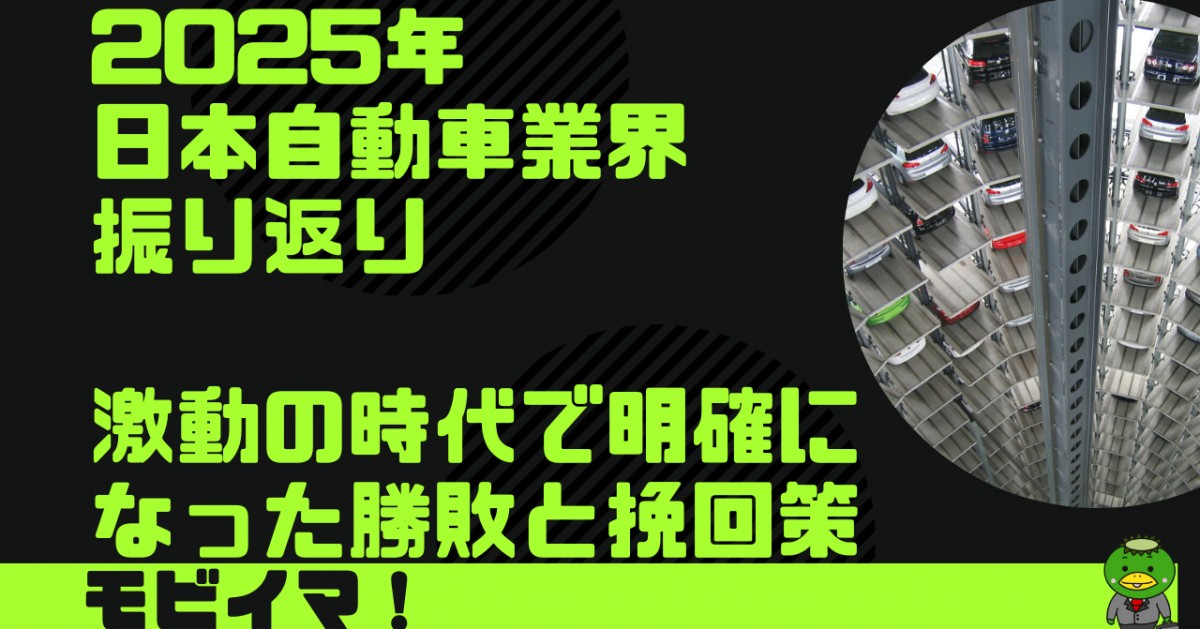【チートすぎる低価格】躍進凄まじい中国BEVが激安な3つの理由
中国自動車メーカーの躍進が止まりません。世界最大の自動車市場、中国。しかし、長年に渡り、外資系メーカーがシェアの大半を占め、「民族系」と言われる中国メーカーはシェアを伸ばすことができませんでした。しかし、コロナ禍以降、状況は一変。BEVを中心とした販売攻勢で一気にシェアを伸ばし、20年では35.7%だった中華系シェアは23年には51.8%、15%以上増加しました。また。海外進出でも頭角を現し、2023年は491万台を輸出し、世界1位に躍り出ました。
なぜここまで成長することができたのか。中国メーカー躍進の1番の要因は「BEVでの低価格」。世界各国がEVシフトを進める中で、中国メーカーは安価なBEVを販売し、非常に高い競争力で他国のシェアを奪っています。他国メーカーがBEVの製造コストに苦しむ中で、なぜ中国メーカーBEVを安く作ることができるのか。その理由を解説します。
圧倒的成長を続ける中国BEV販売

自動車産業は裾野が広く、経済に与える影響が大きいため、中国政府は自動車産業育成に力を入れてきました。2000年代前半では、まずは海外メーカーを誘致し、合弁会社を設立することで技術ノウハウの蓄積とサプライチェーンを構築。内燃機関車ではどうしても既存メーカーの長年の研究開発ゆえに技術力で対抗することは難しく、中国メーカー(民族系)はシェアを伸ばすことが出来ませんでしたが、EVシフトにより状況は変化。動力源がモーターとなり、技術的な参入障壁が下がることで、民族系が相次いで先進的なBEVを投入。政府も補助金で支援することで大幅に販売拡大、20年以降は既存海外メーカーが半導体不足で生産を落としたこともあり、一気にシェアを伸ばしました。長年の悲願であった中国国内での自動車産業育成が実を結んだ結果となり、中国国内、海外を含め、一気に中国「民族系」の存在感が高まっています。
中国国内でのBEV販売台数は2020年には112万台→2023年には669万台。3年間で約6倍にまで成長し、それに伴って、中国国内マーカーのシェアも51.7%、同期間で15%も拡大しました。BEVの中国国内シェアは25%にまで達し、中国政府の掲げていた目標、27年NEV比率45%(PHEV、FCEV含む)を前倒しで達成できる見込みが高まっています。
テスラですら負ける「価格競争」

中国でBEVが大きく伸びた要因は「価格」。他国に比べて、中国国内で販売されるBEVは比較にならないほど安く、ガソリン車並みの値段を実現しています。例えば最も勢いのあるBYD。最も安いBEV「シーガル」の値段は6万9800元。日本円に換算すると、約150万円。日本で言えば、軽自動車よりも安い値段であり、また中国で競合となるガソリン車と同等以下の価格となっています。日本でも360万円で販売されている「ドルフィン」の値段は9万3800元と200万円を割り込む価格。政府からの購入時の補助金は打ち切られていますが(税控除はあり)、補助金なしでもガソリン車に十分に太刀打ちできる価格になっています。
BYDが相次いで値下げ、新車を低価格で投入したことにより、他社も同様の値下げを実施。22年前半頃まではBEVは高級車と超小型EVの低価格車(宏光MINIなど)が中心でしたが、BYDが大衆車価格での販売を開始したこと、また高級車でも同セグメント内では価格を抑えた車種(シールなど)を投入したことで価格競争が激化し、レッドオーシャンとなっています。BEVの先駆者、テスラですら、値下げしても需要は大幅には伸びず、一番大きい工場である「ギガ上海」の稼働を調整する段階に入っており、いかに中国でのBEV競争が激しいのかを象徴する出来事となっています。
価格に加えて、SDVとして車内空間を一新し、運転支援機能を充実させた中国メーカーのBEV。いま中国で求められる大型タッチパネルやカラオケに代表される車内空間の快適性、エンターテイメント性の向上と「映え」を備えた中国BEVは消費者からの支持を集め、一気にシェアを伸ばしたのです。
安さの秘密①:EVの肝「電池」の自国調達

1台150万をも可能にする中国メーカーのBEV。なぜそこまで安くすることができるのか。1つ目の要因は「電池」。電池はBEVの航続距離や充電時間を決定する基幹部品かつ、製造コストの20~30%を占め、コストにおいても極めて重要な部品です。中国メーカーのBEVはこの電池を自国内で調達することができ、他国と比較すると、安い値段で調達できることが安価な販売価格に繋がっています。
2023年の自動車向け電池の世界生産、出荷ベースでのシェアトップは中国、CATL35.6%、2位は自動車メーカーでもあるBYDで15.6%、2社で全世界の50%以上のシェアを占めています。トップ10内の企業のうち、中国メーカーは6社。
中国は電池の完成品だけでなく、部材となる原料のシェアも高く、負極に欠かすことのできない黒鉛では90%以上、リチウムでは生産量は13%のみですが、精錬工程では5割を超えるシェアを占めています。黒鉛の生産やリチウムの精錬ではその過程で多量の環境負荷物質も排出されるため、その処理のための投資が莫大になります。欧米や日本ではコンプライアンスやSDGsの観点から、環境負荷物質の対応が必須となりますが、中国や新興国では絶対的ではありません。周囲の環境を悪化させながらも、投資をせずに安価に生産できる状況にあります。コンプライアンスによるリスクの差が製造コストに反映され、中国と他国で生産する電池に価格差が生まれてしまうのです。自国の環境を供物に捧げて、安価な電池を生み出しているともいえでしょう。
安さの秘密②:赤字覚悟のバーゲンプライス

電池のコストが低いとしても、ガソリン車並みの価格にするには不十分です。どれだけ電池のコストが下がったとしてもガソリン車の内燃機関と比較すれば高額であり、現在の価格を実現することはできません。さらに価格を下げる要因、それは「赤字前提での価格設定」です。
中国では政府の後押しもあり、新興の電気自動車メーカーが乱立していますが、その中でも黒字になっているのはほんの一握り。2023年の業績で電気自動車メーカーで確実に黒字なのは、BYDと理想汽車の。その2社はPHEVを販売しており、BEV専業ではありません。BEV専業メーカーは軒並み赤字であり、一部のメーカーでは採算が改善しているものの、競争の激化もあり、黒字化の目途が立っているメーカーはほとんどありません。
先日、販売が公表され話題になったシャオミが投入する初の電気自動車「SU7」。非常に高機能でありながら、標準モデルの価格は21.5万元、日本円では450万円~と破格の値段。ただ1台当たり150万の損失が発生するとの試算もあり、「儲かる」クルマではありません。
「BEVはこれから成長が見込まれるために、先行してシェアを獲得し、現状は赤字であっても将来的に採算がとれるのであれば問題ない」という戦略のもと、価格競争が激化し、他国の自動車価格が上昇する中で、中国の自動車価格は下がる、世界とは逆のトレンドになっています。2023年7月では、こうした価格競争の激化に対して、中国国内でも懸念の声が上がり、「異常な価格設定」に対し、見直しを求める合意が発表されましたが、わずか2日後に撤回。その後、より価格競争が激化しており、各社は「赤字覚悟」で値付けを行い、世界で類を見ないほどの低価な販売が続いています。
安さの秘密➂:多額の政府からの補助金とVC・銀行からの融資

業績が赤字であっても、事業が存続していける理由。それは手元の資産が途切れていないからです。赤字であれば、資産は出ていく一方のはずなのに、なぜ資産が尽きないのか。その理由は、政府やVC(ベンチャーキャピタル)からの多額の補助金、融資にあります。
ドイツ、キール研究所のレポートによれば、中国の産業補助金額はOECD諸国の少なくとも 3 ~ 4 倍、最大で 9 倍にも達し、国家が定める重点分野であるEVにも多額の補助金が投入されています。BYDでは22年だけで約3500億円もの補助金を受けており、その上工程である電池なども同様の補助を受けており、その恩恵は計り知れません。中央政府からだけでなく、各地方の省からの補助、重点分野では銀行の融資も手厚く、また多くのVC(ベンチャーキャピタル)からも出資がなされています。
中国は国を挙げて、EV産業の振興を後押ししており、補助金が多くの企業の存続を支えています。ただ、中国メーカー内でも鎬を削る争いがなされ、競争がより激化する中で勝ち残るのはほんの一握り。中国電動自動車百人会でBYDで王会長は「新エネルギー車は荊棘の道であり厳しいトーナメント戦」と述べているように、補助金を受けた中でも今後淘汰が進み、真に「強い」企業だけが勝ち残る。中国でいわば「蟲毒」の状態を勝ち抜くためには、何よりも販売を伸ばすことが重要。そのために、資金調達ができる範囲で、価格を下げ、たとえ赤字を継続してでも台数を優先する戦略がとられ、結果大きく販売価格は下がっています。
「チート」と言えるほどに安い中国車の販売価格。既存メーカーとは全く違う戦略がとられ、価格だけで言えば、追い付くことは不可能と言える状態です。価格で負ける既存メーカーはいかに戦っていくのか。採算と台数、どちらを優先するのか。その選択が今後の自動車メーカーの将来を決めていくことになりそうです。
・CASEなどの業界トレンドを詳細に解説
・各自動車メーカーの戦略や決算分析
すでに登録済みの方は こちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績