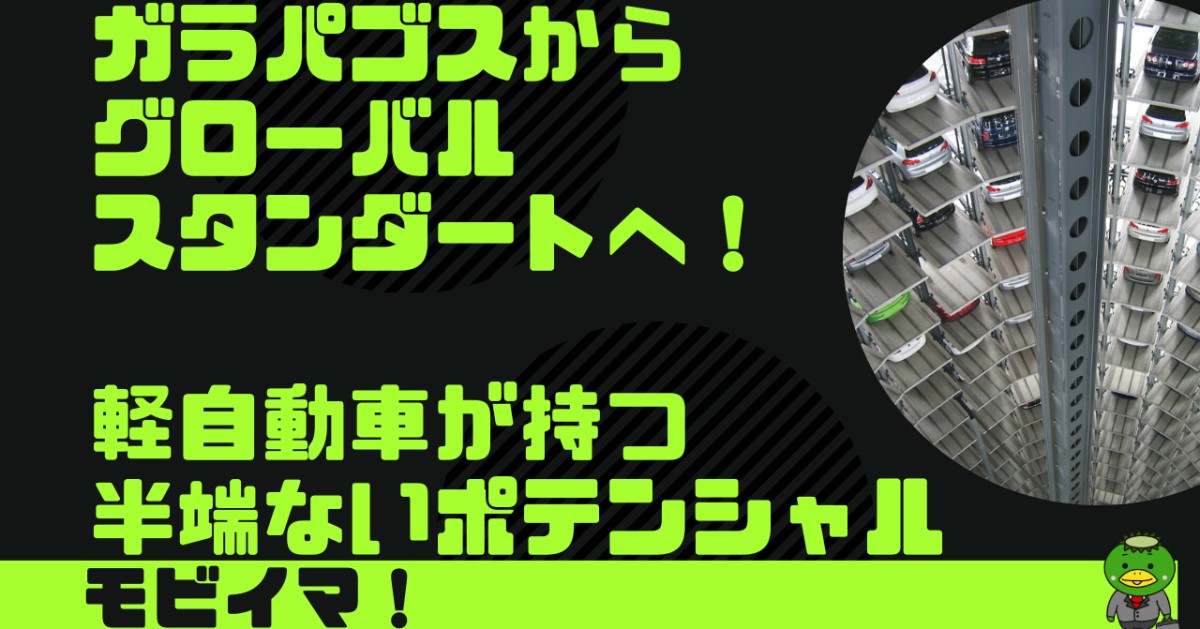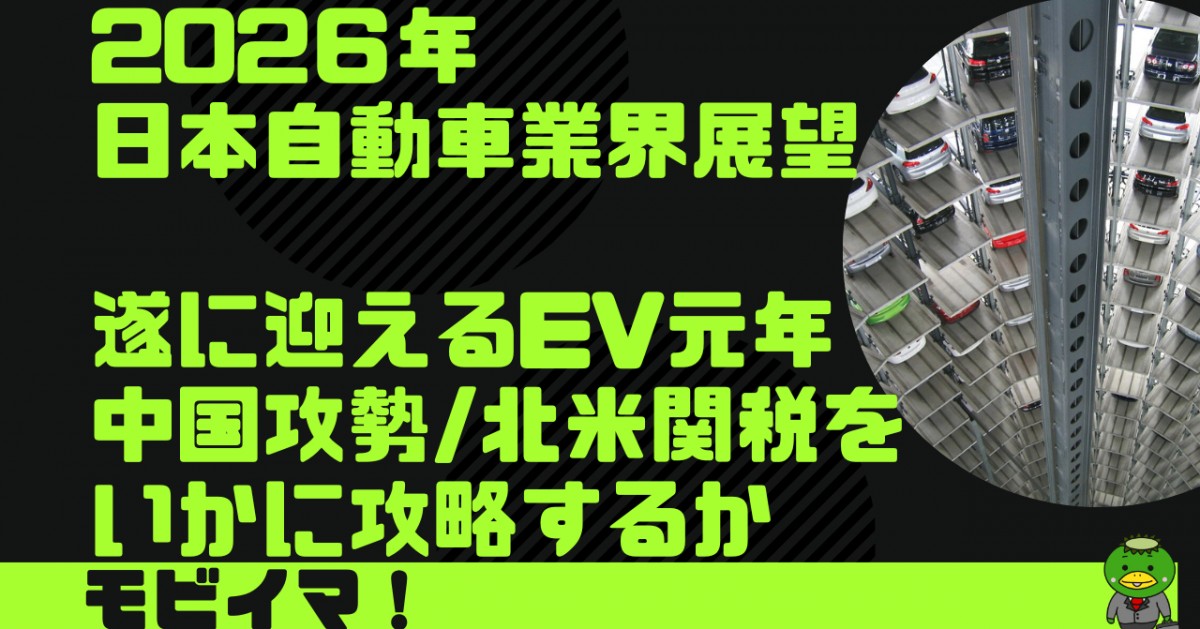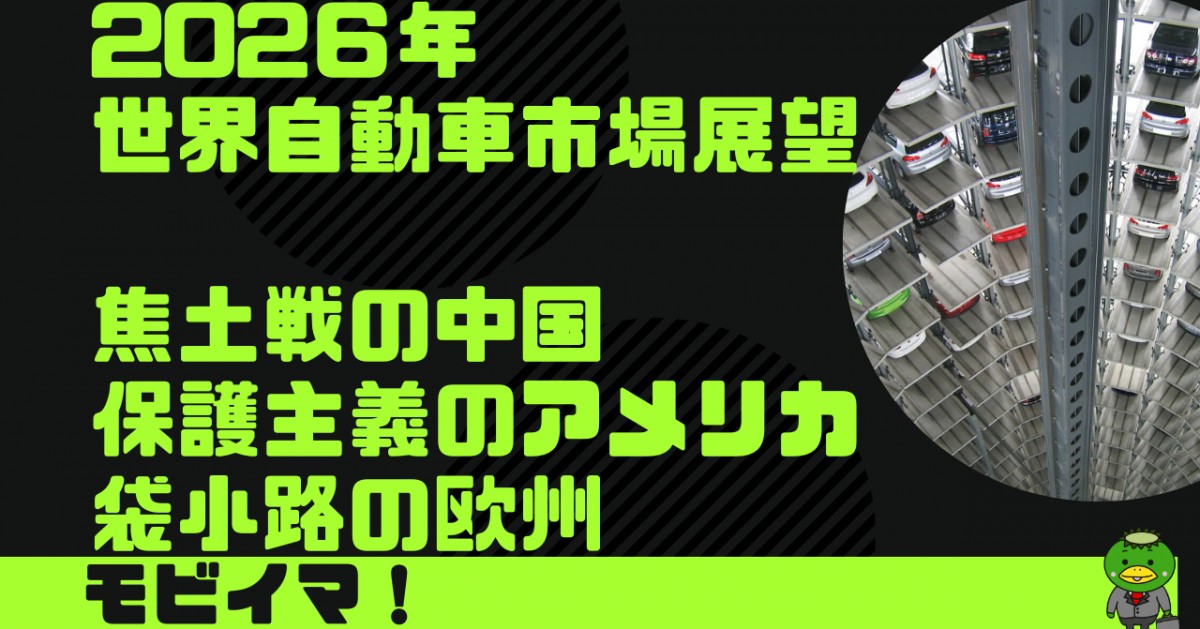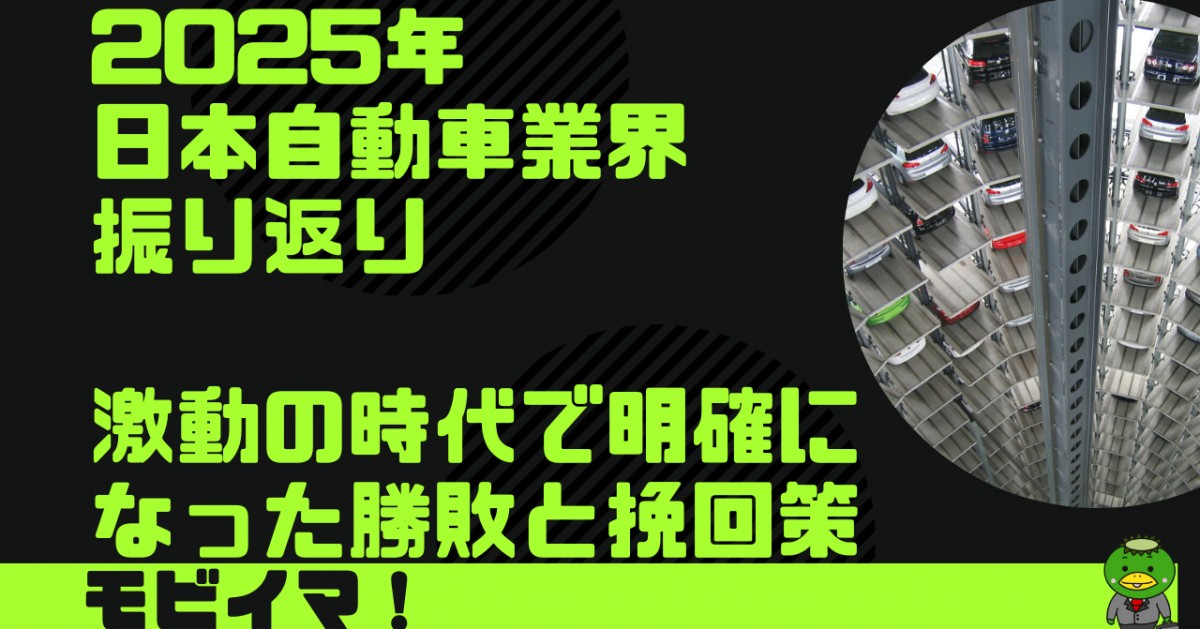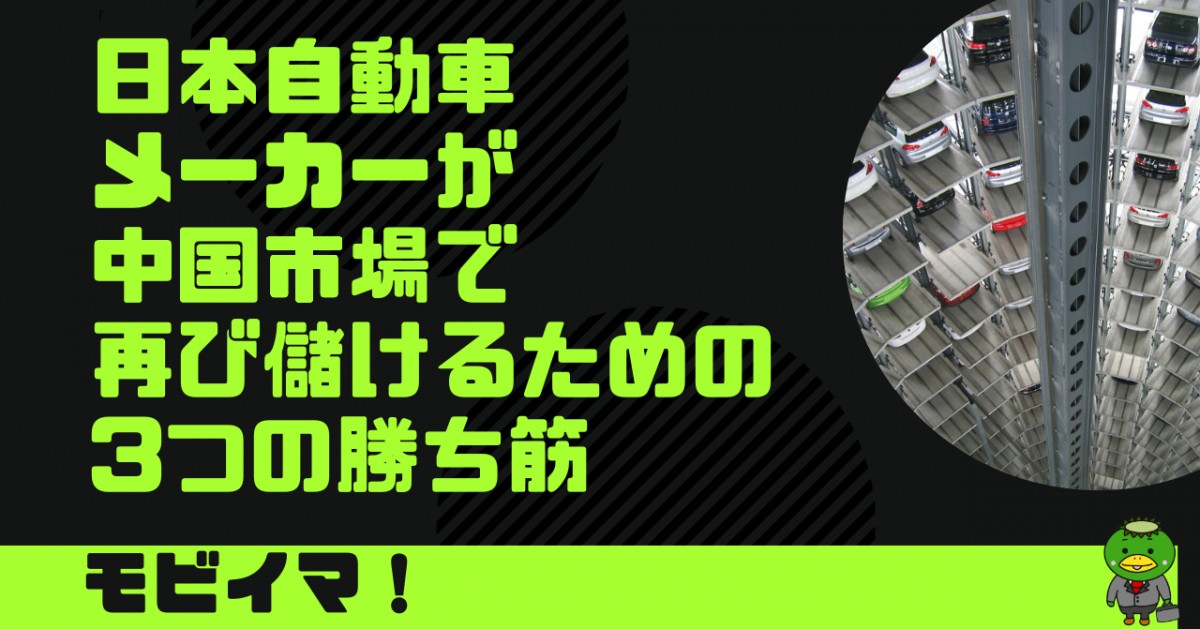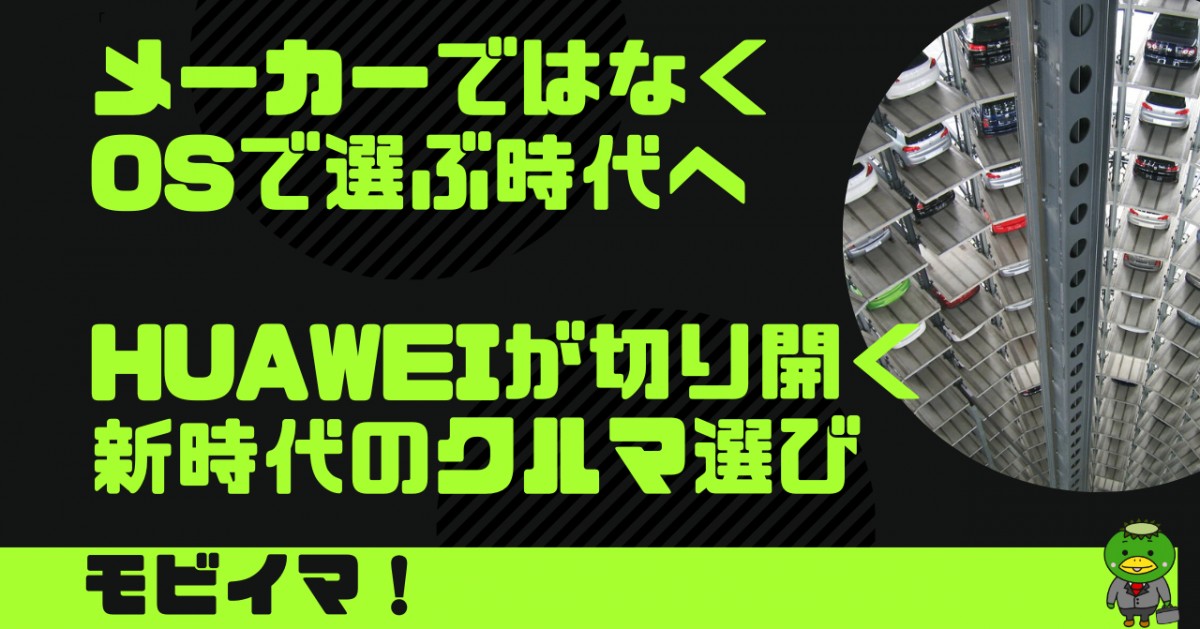【テスラ化するトヨタ?】EV戦略転換報道が示す自動車業界の現状
ご安全に。
今期の戦隊シリーズ「ドンブラザーズ」がインパクトが強すぎる展開で毎週ビックリ、カッパッパです。同じ仲間の中で元カノを巡る戦いが…って子ども向けでどないやねん。
今回は先週報道のあった「トヨタEV戦略転換」を自動車業界の中の人目線で読み解いていきます。遅れていると指摘され、bZ4Xでもハブ問題のリコールで躓いたトヨタのEV。昨年12月、2030年350万台の目標を掲げましたが、その戦略も1年かからずに見直しに?
記事の信ぴょう性は正直定かではないのですが、状況が変わりゆく中で、EV戦略の見直しを迫られていることは間違いなさそう。記事の内容で言及されている戦略の内容と共に、なぜ今見直しが求められるのか、そして戦略が変わったとしたら、具体的にどのようにトヨタはEVを作っていくのか。
今回の情報元の「事情に詳しい関係者4人」は見つかったら、懲戒になってしまうのではないか、プラットフォーム見直しするのであれば見るたびに危ない読み方を考えてしまう「e-TNGA」の名前は変えた方が良いのではないか、「業界全体では2030年に5400万台のBEV生産が計画されている。これは全世界の年間生産全体の50%以上に相当」なんて希望的数量の積み上げやんけ、など些細な点まで突っ込んでしまいたくなるこの記事。モビイマ!では、今回でしか読めない濃い解説でお送りします。
報道されたトヨタEV戦略の概要
[24日 ロイター] - トヨタ自動車が電気自動車(EV)事業を巡り、戦略の修正を検討していることが分かった。基本設計のプラットフォーム(車台)も見直しの対象に含めており、2030年までにEV30車種をそろえるとしていた従来の計画の一部は既にいったん止めた。想定以上の速度でEV市場が拡大し、専業の米テスラがすでに黒字化を達成する中、より競争力のある車両を開発する必要があると判断した。
24日にロイターが発信した「トヨタEV戦略見直し」報道。ロイターという一定の権威性を持ったメディアであること、具体的でインパクトのある内容であったことから、自動車業界の方のみならず、世間一般でも大きな話題となりました。
前半部分の内容を簡単にまとめると…
-
2021年12月に発表した2030年350万台のEV戦略を見直し
-
一部車両の開発計画を停止(小型SUV「コンパクトクルーザー」や「クラウン」のBEVも含む)
-
見直し理由は「EV市場が急速に立ち上がり、車両の価格が徐々に下がるなか、現在の計画(e-TNGAのプラットフォーム使用)では採算が伴わず、競争力がないから
-
今年半ばに検討チームを設置。技術開発トップなどを歴任した寺師茂樹エグゼクティブフェロー(67)が主導し、来年初めまでにBEVプラットフォームの見直しを含めた技術戦略を検討。
内容を見るとかなり大規模な見直し。プラットフォームの開発は販売戦略の肝であり、開発工数も膨大。見直しするとなれば、いつ同様な車種が出てくるのか、生産されるのかも大きく変わってきます。具体的な個人名まで出されているだけに、信ぴょう性は高そうに思えます(というかリークした人は一体何者なんだろう)
プラットフォーム見直しによる影響
そもそもプラットフォーム、TNGA(Toyota New Global Architecture 読み方は「ティーエヌジーエー」)です。ってなんやねんというところから解説すると
TNGAはクルマの設計思想であるArchitectureから変えていく取り組みで、パワートレーンユニット(エンジン、トランスミッション、HEVユニット)とプラットフォーム(車台)を刷新し、一体的に新開発することで、「走る、曲がる、止まる」というクルマの基本性能を飛躍的に向上させ、いつまでも「愛車」と言っていただける商品力に高めることをめざします。
車両のベースとなる車体を共通化し、性能また開発効率を向上させるのがプラットフォームの目的。プラットフォーム化はトヨタだけではなく、日産などでも取り入れられ、海外メーカーでもすでに導入がされています。EVで開発費が増える中で少しでも効率よく、良いクルマを作るためにはプラットフォーム化は当然の戦略。
部品メーカー視点からすると、プラットフォーム化により部品の共通化が進んでいくため、部品が採用されれば非常に大きな数量になる⇒失注すると大幅減に。モジュール化も含め、1部品に占める売上が大きくなるため、受注できるかどうかが非常に重要になってきます。そのため、今回プラットフォーム見直し、これまで開発していた車両の開発停止、新規プラットフォームへの移行がなされるとすれば、部品メーカーの戦略にも大きな影響が出てくるでしょう。
ICEとの混流ライン⇒EV専用ラインへ
今回の見直しのポイントは現在のトヨタ、EVプラットフォーム「e-TNGA」に競争力がない、その理由が「トヨタは内燃機関車からEVへの移行にはしばらく時間がかかると予測し、ガソリン車やハイブリッド車と同じラインで生産できるよう設計」されていたとされる点です。
現に「e-TNGA」を採用している「bZ4X」は元町1ラインで流動されていますが、このラインでは他に『ノア』『ヴォクシー』『MIRAI』を生産。ICE、FCEV、BEVが流動する混流ラインとなっています。
このトヨタイムズの記事を読めばわかるのですが、1つのラインで複数の車種を流すためには様々な工夫が求められます。流す車種を変えるごとに設備の変更、調整(段取り)を行い、単一車種を流すよりも生産効率は低下します。加えて車種ごとに使用する部品が異なるため、部品の置き場も専用ラインより多く構えておかなくてはいけません。ICEとBEVでは変更点も大きいため、段取りや部品の変更点も増えてしまいます。
専用ラインの欠点とは?
生産効率が悪いのであれば、そもそも専用ラインにすればいいんじゃないのかと思われるかもしれません。ただ専用ラインにも弱点はあります。それは需要の増減(特に減)に極めて弱いということです。
需要が十分にあり専用ラインの能力を満たすだけの生産ができれば、一番コストを低く作ることができるでしょう。しかしながら、自動車の需要を読むのはなかなか難しい。需要が減り、専用ライン能力以下の生産=稼働率が低下すれば、1台当たりにかかる設備償却費が増え、コストが上がってしまいます。自動車産業は設備産業であり、1つの生産ラインを作るコストは膨大。そのため、稼働率の低下は大きく損益に影響し、一気に赤字になってこともあり得ます。自動車メーカーが赤字に転落する典型的なパターンは「拡大路線で工場新設⇒計画よりも売れずに稼働率低下⇒稼働率を上げるために値下げ攻勢⇒ブランド力、1台当たりの利益低下⇒業績赤字化」。
混流ラインは複数車種を流せるために柔軟に需要に対応できることが利点であり、自動車メーカーは過去の反省から、混流ラインでの生産を行っているのです。(トヨタ以外、マツダでも「スイング生産」として実施」)
・専用ライン⇒多量少品種生産(コスト低、柔軟性小)
・混流ライン⇒少量多品種生産向(コスト高、柔軟性大)
これで覚えておけば大丈夫!
またトヨタはすでにグローバルで非常に多くの工場を保有しています。各工場の設備、投資の償却が終わる前に新ライン、専用ラインを作るとなると、一気に固定費が増えます。既存ラインを活用し、ICE、BEVを並行して生産する戦略は初期投資の額を抑え、業績を維持するためには妥当な戦略です。
テスラ化?ギガプレスと熱管理
この記事の後半で触れられていたのは製造技術、そしてこれから力を入れる部品の詳細。
テスラが生産ラインに導入した大型のアルミ鋳造機「ギガプレス」の有用性も検討する。自動車のプラットフォームは数百点の鋳造品や金型成形品を溶接して組み立てるが、大きな鋳造品を作れるギガプレスはこれを大幅に減らして効率化できる。
テスラで専ら話題のギガプレスの採用。こちらは車体の作り方を大きく変えるだけに設備投資も莫大ですが、その分コスト低減幅も非常に大きい。車体の修理が非常に高額になるデメリットはあるのですが、初期の車体価格を下げるという点では有効な手段。
関係者3人によると、競争力向上のために重要な技術はさらに2つあり、1つはグループ会社のアイシンが開発している第3世代「eーAxle」。e-TNGAを初めて採用したEV「bZ4X]に積んだ駆動装置のおよそ半分に小型化している。
「eーAxle」⇒モーター、インバータ、減速機が一体となった駆動部品はクルマの「走る」性能を大きく変える基幹部品。トヨタグループではアイシンが開発を進め、現在は第1世代が量産化、技術革新は進んでおり、記事にあるように第3世代までロードマップが示されています。トヨタグループの強みを活かして、性能の高い「eーAxle」を搭載できれば、魅力的なBEVが出てくるでしょう。
もう1つは電池やモーターの排熱や車内空調など、熱を一体的に管理する技術。デンソーとアイシンが最優先で開発に取り組んでいると、関係者の2人は話す。e-TNGAを使った現行のEVは排熱を捨ててしまうことがあるが、テスラ車は暖房に活用するなどしている。省電化が可能になることから電池量を減らすことができ、生産コストの削減にもつながるという。
もう一つは熱管理。これはテスラ車ですでに「オクトバルブ」として採用されている技術。熱を効率的に活用(暖房や電池の冷却など)することで、省エネ化、燃費効率が向上。航続距離が重要になるBEVではより重要性を増す部品。
生産ライン、製造技術、部品開発。この記事でも言及されているようにテスラの後を追っているように見えるトヨタ。テスラは今世界の自動車メーカーの中で最も稼いでいるメーカー(高級車専門除く)。「儲かっているところがわかってから、後出しで追い付いてぬかしていく」これまでのトヨタの戦略から考えると、テスラの真似をするのは当然なのかもしれません。
なぜ今、見直しなのか
ただ昨年12月に出したBEV戦略がもう見直しになったのはなぜなのでしょうか。それは想定以上に進んだ中国、アメリカのEVシフト。中国でのNEV(BEV+PHEV)の数量は当初の予測を大きく上回り、今年600万台に達する勢い。特にBYDの躍進はすさまじく、安価な車両を世界展開し、利益も出ている現状は完璧に想定外でしょう。またアメリカではバイデン政権が大規模なBEV支援策を打ち出し、当初の見込みよりもBEVの普及が早く進むことが見えてきました。ビッグ3もBEVに本腰を入れ、BEV受注状況は非常に好調です。
加えていうと半導体供給不足により車両価格が大きく向上していることもBEVの普及を後押ししています。アメリカでは新車の販売価格は過去最高記録を更新。BEVはどうしてもICEと比べ、価格は高くなりますが、自動車全体の価格が高騰しているために、その価格差は想定的に低くなっています。テスラのモデルYが600万近い値段ながら、売れ行き好調なのも、その点の影響が大きいでしょう(あと納期が比較的短い)
加速し続けるBEVシフト。予想を超えるスピードにより、1年もたたずにトヨタはBEV戦略の見直し検討が必要になったのです。
新ラインはどこにできる?
ではBEVの新ライン、専用ラインができるとしたらどこになるのか。「アメリカ」が最有力候補。BEVでは補助金対象を自国生産に限定するといった各国が保護主義政策を取られています。アメリカの規制は特に厳しく、BEVの主要部品である電池の材料を含め、囲い込み(というか中国脱却)が求められます。アメリカはトヨタの主要市場であり、EVシフトが急激に推し進められていることから、EV専用ラインができる可能性は高いでしょう。(ホンダはすでにアメリカに専用ラインを作ることを発表済)
もう一つの巨大市場、中国は地政学的なリスクも大きく、大規模な投資を行うことはできるのかは難しい判断に(直近のロシア撤退のニュースを考えると、慎重にならざるを得ない)。EV推進が進んでいる欧州、トヨタはそこまでシェア高くないため、初期での優先度は高いとはいえず、新ラインを引いていく可能性は低そうです。
じゃあ日本で!となるかもしれませんが、上記のようにBEVは自国生産優遇がされているため、輸出に向かず、日本で生産してもあまりメリットはありません。現段階では日本のEV市場は大きいものではなく、自国内での消費がそれほど伸びず、稼働率が下がってしまう可能性があります。ただ現在の1$=150円の円安がこのまま続くようであれば、世界の輸出工場として日本への投資の可能性はあります(自国内なのでいろいろ準備や都合もつきやすそう)
もう一つ可能性が高いのは東南アジア、特にタイ。政府からのBEV優遇政策が強く押し出され、工場誘致に積極的。中国のBYDも工場進出を決めており、ASEANのハブ工場としてEVラインが新設される可能性はあります。
報道の信ぴょう性については疑問がありますが、年々加速していき、予想を超えるEVシフトに対し、トヨタも戦略を変えていく必要があることは間違いなし。良い見方をすれば、現段階で見直しが入ることで、EV普及が本格化する20年代後半から、競争力のある魅力的な車種が販売⇒世界一のトヨタがポジションを維持…ということになれば、ベスト。
本当にBEV戦略は見直されるのか。昨年12月のような大々的な戦略発表が再び行われるのか。何かと読み方に困る「TNGA」(テ〇ガと呼んではいけません)、プラットフォームの名前は果たして変わるのか。日本経済全体にも大きな影響を与えるトヨタのBEV戦略、要チェックです。
・CASEなどの業界トレンドを詳細に解説
・各自動車メーカーの戦略や決算分析
すでに登録済みの方は こちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績