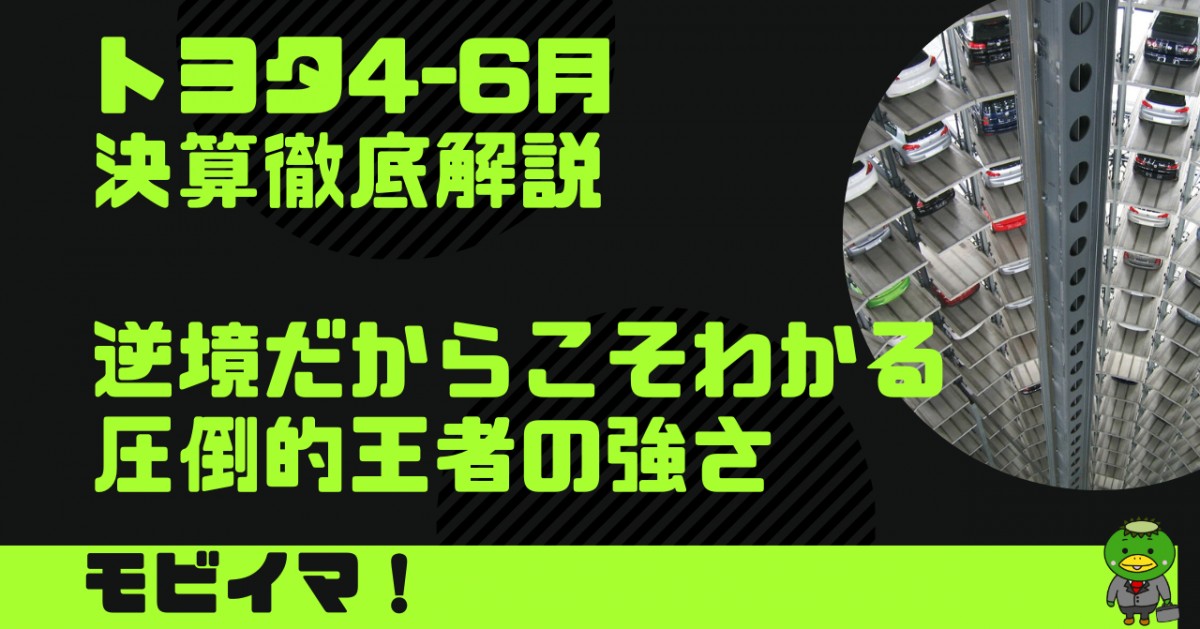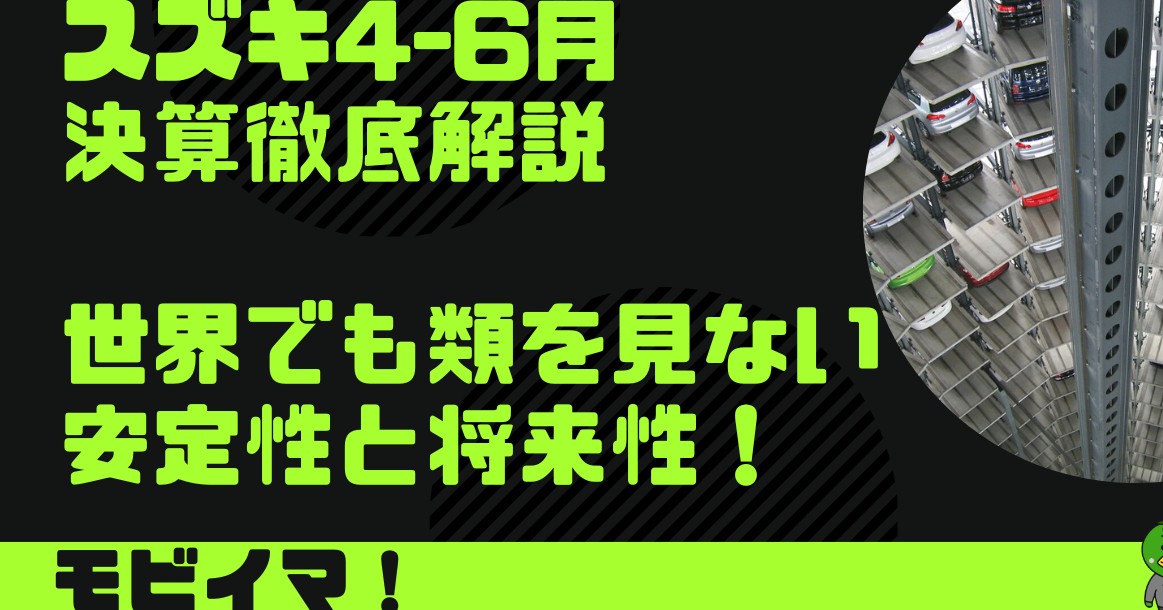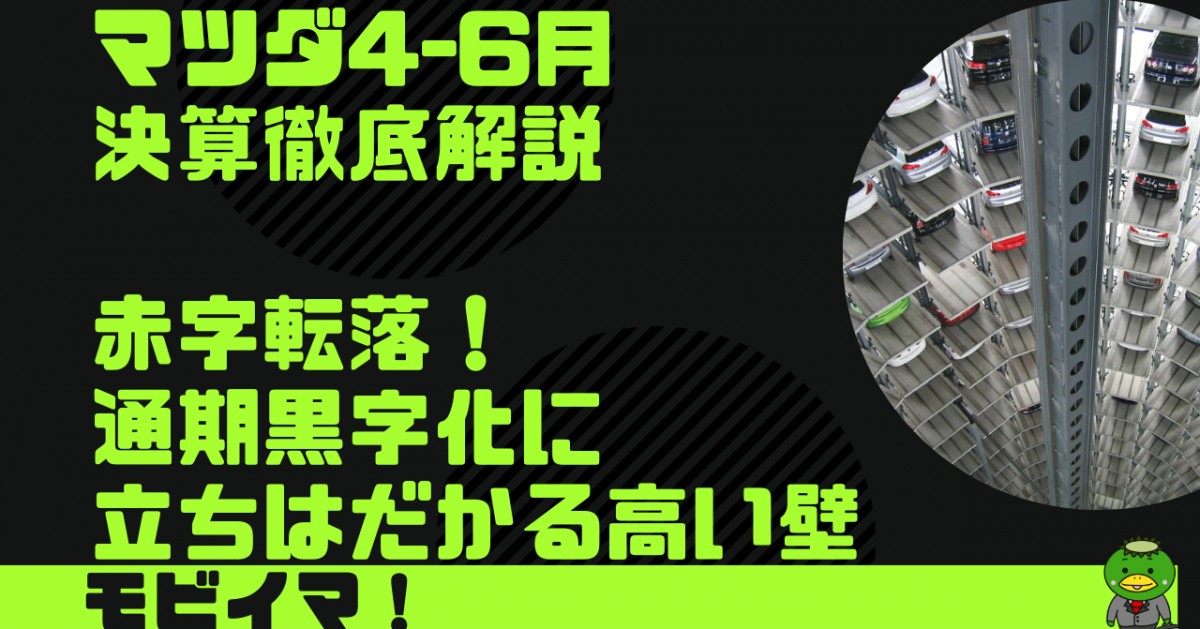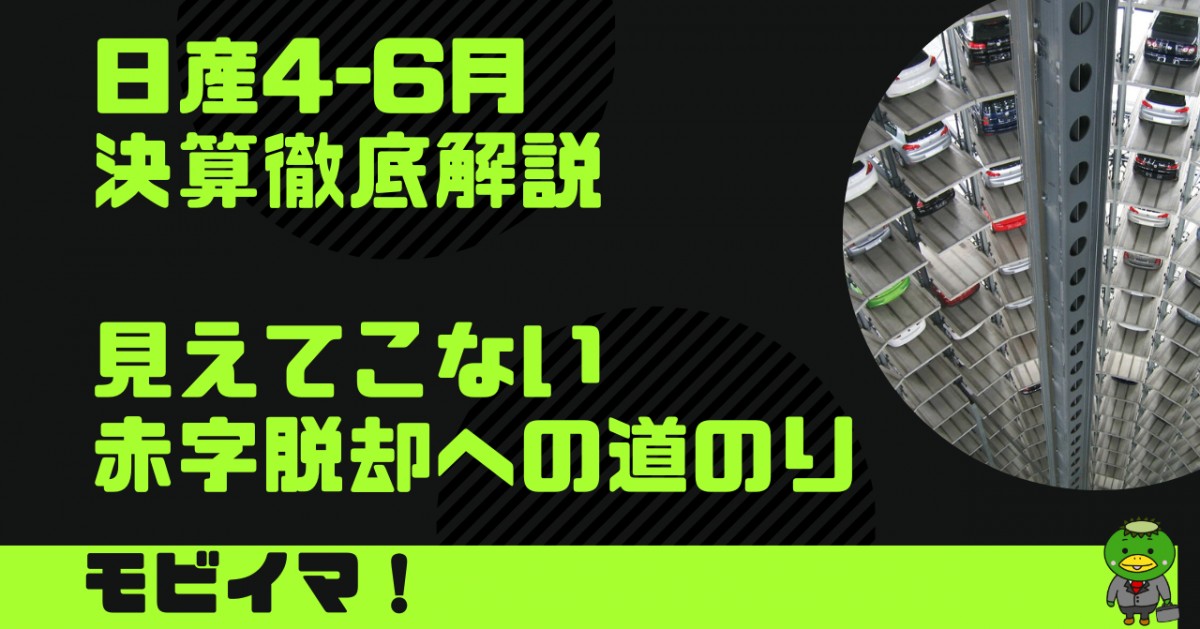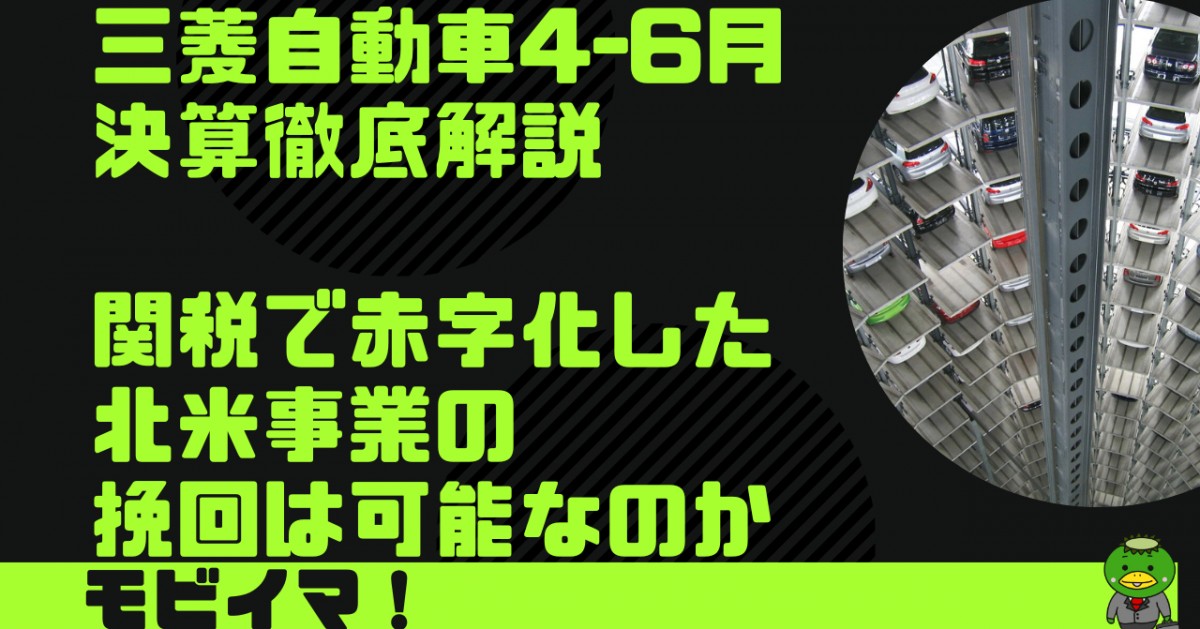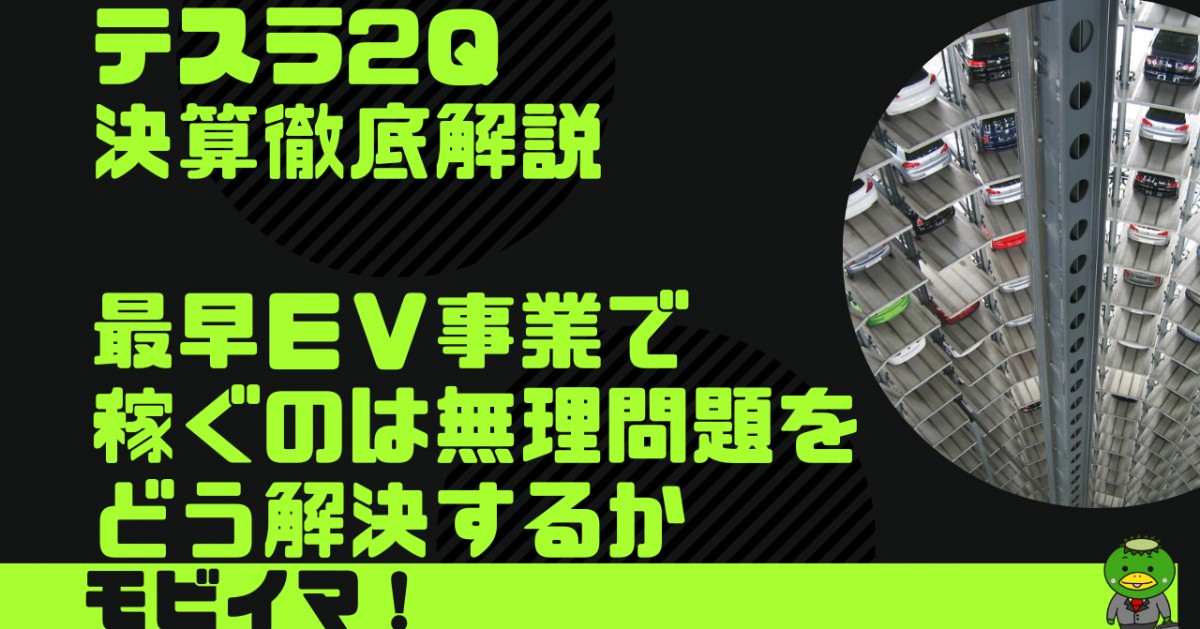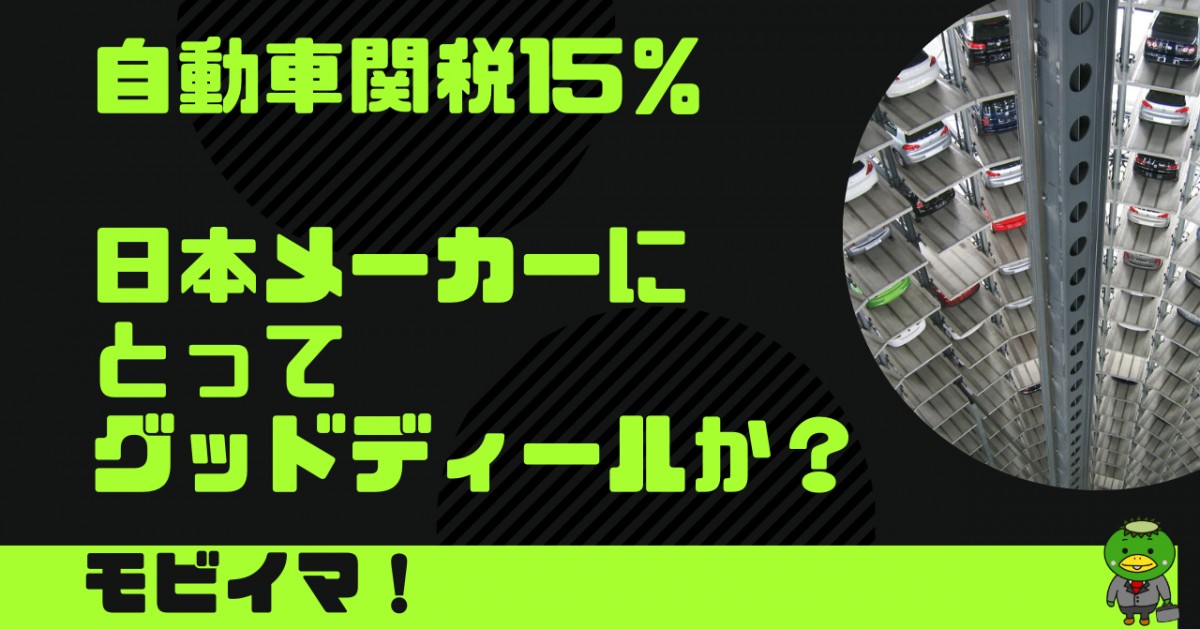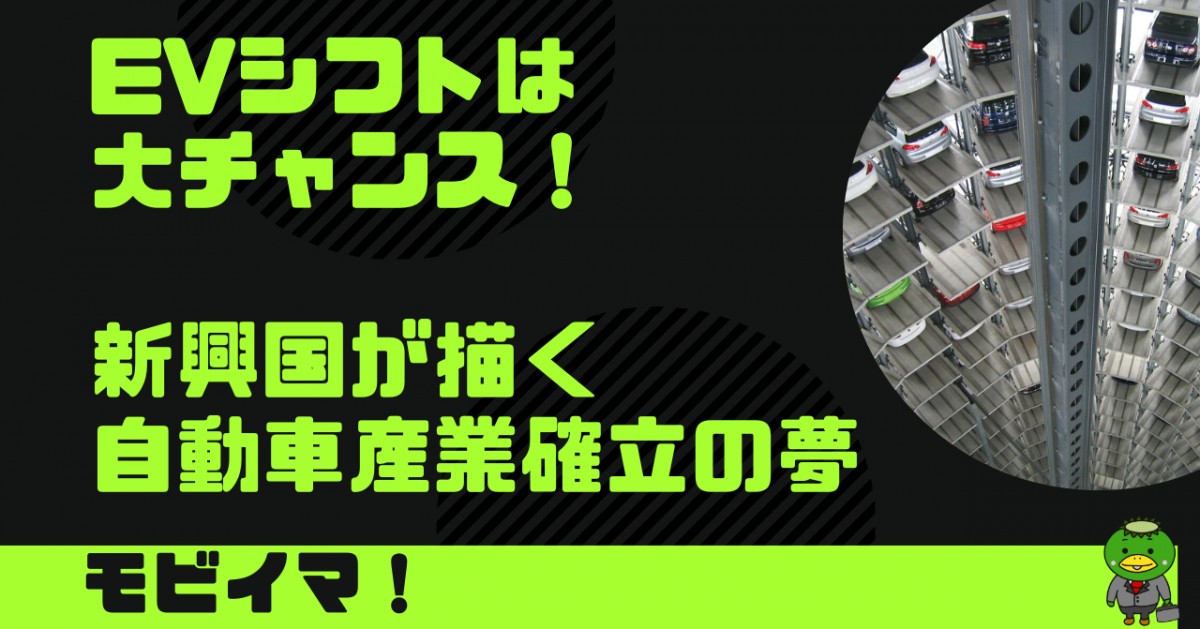【見えてきた急成長の歪み】中国自動車メーカーが直面する『内巻』という試練
躍進を続けてきた中国自動車メーカーが今、岐路に立たされています。中国自動車メーカーは、ここ数年で新エネルギー車(NEV)の普及と共に驚異的な成長を遂げてきました。しかし、この急速な「躍進」の裏側では、いくつかの深刻な「成長の歪み」が生まれ、直近その問題が顕在化しています。果たして中国自動車メーカーは、このまま右肩上がりでの成長を続けることができるのか。この記事では、中国自動車メーカーが直面する現状と、今後の展望について詳細に分析します。
65%にまで達した中国市場シェア
2025年4月での中国市場における中国系の自動車メーカーシェアは65.5%。2020年が35.7%だったことを考えると、この5年で30%も増えたことになります。中国自動車市場は世界最大、販売台数は年間3000万台以上。単純計算で中国自動車メーカーは5年間で900万台、販売台数を増やしているのです。
その一番大きな要因は中国での新エネルギー車(NEV)の普及が進んだこと。内燃機関車では海外メーカーと中国自動車メーカーの間では、エンジンでの技術力の差もあり、競争力に劣り、シェアを伸ばすことができませんでした。ただ、NEVではエンジンはPHEVの一要素となり、車両における性能の差は内燃機関車よりも少なくなります。中国自動車メーカーは政府からの支援も受け、魅力的なNEVを販売していくことで大きくシェアを伸ばしました。中国自動車メーカーは新興メーカーが多く、新しい技術、特にソフトウェアを中心とした開発を進め、顧客体験を重視したSDVの機能を高めたことも販売台数増の大きな要因となっています。自国での販売台数増を足掛かりに中国だけでなく、世界各国へも進出。世界第1の自動車輸出国となり、今年2025年に入ってからも右肩上がりで成長を続けています。
飛ぶ鳥を落とす勢いで急成長を遂げた中国自動車メーカー。ただ直近、その急成長の歪みが見えはじめ、徐々に状況は変わりつつあります。
激化する「内巻」競争が生み出す収益性の危機
今中国 自動車業界で一番の問題となっているのは、熾烈な価格競争です。5月23日、中国自動車市場で販売台数TOPのBYDが、22モデルを対象に値下げを発表しました。その値引き率は最大34%。業界最大手の値引きに対し、吉利自動車、奇瑞自動車など多くの自動車メーカーが追随し、価格競争が一段と激化しています。グローバルで見た場合、インフレに伴う原材料高などにより、自動車価格は近年上昇傾向にあります。中国自動車市場は世界の中で特異点。価格競争が進み、この数年で自動車価格は下降。 2024年には200以上の車種が値下げされ、2025年に入ってからも、その傾向は変わっていません。
あまりにも過熱した価格競争は完成車メーカーの「消耗戦」となり、収益率は大きく低下しています。国家統計局によると、かつて7%~8%あった自動車産業の売上高利益率は、2024年は4.3%、2025年1月~4月には4.1%に低下。値下げは原価低減などの製造コストを下げた結果ではなく、外部要因での競争激化、販売台数維持、促進のために行われ、完成車メーカーは疲弊しつつあるのが現状です。
こうした現状を指し示す言葉として中国で使われているのが「内巻」。「involution」という英単語の訳語で、激しい受験戦争や長時間労働を伴う出世競争など、中国の社会情勢を反映した言葉として、2020年ごろからネット上で流行。現在は「内向きな過当競争で全体の効率が低下、全員が疲弊する」という意味で使われ、特に産業界での過当競争に使われるようになっています。自動車業界だけでなく、鉄鋼や太陽光パネルでも同じ問題に直面しています。
「内巻」を生み出す政府の方針
「内巻」が生まれる要因は中国政府が打ち出す「製造強国」を目指すための政策です。 中国政府は2015年に「中国製造2025」を発表。目標達成に向け、中央・地方、双方の政府が補助金や税制優遇などで企業を積極的に支援してきました。特に「新三様=新・三種の神器」EV、太陽光パネル、リチウム電池には手厚い支援が実施され、実際に大きな効果を上げています。
一方で、弊害として生まれたのが「内巻」。政府からの補助金を目当てに、新規参入が相次ぎました。EVメーカーは、ピーク時には500社にのぼったと言われていて、いまも企業数は減ったものの、依然50社程度が製造を手がけているとされています。また、市や省の間で企業の誘致合戦が激化し、市や省ごとに各産業のサプライチェーンが構築。非効率な生産体制と過剰生産を生み出しました。中国の自動車生産能力は約5000万台とされ、約3000万台の販売から考えると能力は過剰であり、台数を少しでも伸ばすために価格を下げる→収益性が下がるという悪循環に陥っています。
直近では新興メーカー哪吒汽車が破産。哪吒汽車は2018年6月にブランドとして正式に発表された、比較的新しい電動車メーカーです。主に若年層をターゲットにしたリーズナブルでハイテク志向のEVを展開し、販売価格帯は一般庶民にも手が届く設定で、都市部の中間層を中心に着実にファンを獲得。2022年では年間15.21万台という販売台数を記録し、新興EVメーカーのなかで販売実績トップに立つ快挙を達成。タイでの現地生産も開始し、海外へも進出し、有望な新興メーカーとされていました。しかし、2023年からの補助金の段階的な削減、市場の競争激化により、販売台数の減少に直面し、収益が減少、資金繰りも悪化。製品開発のペースも鈍化。経営の立て直しを試みるも、減産、コスト削減、リストラなどの施策は負のスパイラルを断ち切るには至らず、今回破産に至りました。
破産に至らないにしても収益性の悪化は他社共通の問題です。中国の新興EVメーカーでも、注目されてきた蔚来汽車(NIO)は直近2025年1~3月期の決算で、純損益は67億5000万元(約1345億円)の赤字を計上。前四半期もほぼ同様の損失となっており、資金繰りに懸念が及ぶほど採算性は悪化しています。中国メーカーの中で黒字なのはBYDなどの数社に限られています。多くの企業は激化する市場の環境の中で台数を少しでも確保するために、赤字前提の値下げを行いながら、販売を続けています。
より厳しいのは完成車メーカーではなく
「内巻」の影響を受け、疲弊しているのは完成車メーカーだけではありません。自動車業界全体、販売店や部品メーカーも多大な損害を受けています。少しでも価格を抑えるため、完成車メーカーは多大なコストダウンを部品メーカーに要求し、部品メーカーでも採算性が低いことに苦しんでいます。部品の調達価格は年間10~15%も引き下げが要求されているとされ、この容赦ない圧迫は、サプライヤーの財政健全性と存続可能性に影響を与えています。中国国内部品メーカー中からもこうした現状に不満の声をあげられています。
コスト削減への強い圧力は、品質を犠牲にするというリスクを生み出します。これは中国語で「以价换量(yǐ jià huàn liàng)」といわれ、「価格を量と交換する」ことを指します。低品質な材料の使用から、製造プロセスの手抜き、あるいは財政的に多大な圧力を受けているサプライヤーからの安価な部品調達まで、様々な形で品質を担保しない部品が使われる可能性があります。
販売店の現状も深刻です。販売店は価格競争の矢面に立たされ、大きな損害を被っています。特に損害を与えているのは「価格逆転」。相次ぐ値下げによって、販売店がメーカーから仕入れた価格よりも安く車を売らざるを得ない状況を指します。多くの販売店にとって、新車販売は、今や赤字を出す活動へと変貌しているのです。赤字でも自動車を販売するのは、メーカーが設定した販売目標を達成し、年末のリベートを得るためですが、リベートもは常に報われるとは限らないギャンブル。こうした中で販売されたことにして、名義を変更し、ゼロキロ中古車(新古車)にすることがまん延し、市場全体の車両価格を押し下げる悪循環に陥っています。厳しい環境の中で販売店の倒産も相次ぎ、2024年では4000店もの販売店が撤退、閉鎖されたという報道もあります。
販売店の減少はメンテナンスおよび修理サービスの質、適時性、信頼性の低下を招き、ユーザーにとって深刻な問題です。特にNEV所有者にとっては大きな痛手となります。NEVに搭載されている高度なソフトウェア、インテリジェント機能、複雑なバッテリーシステムは、アップデート、診断、専門的な修理のために、継続的で高品質なアフターサービスに大きく依存しています。ディーラーが閉鎖したり、自動車メーカーが破産したりすれば、重要なソフトウェアアップデートや専門的なメンテナンスが受けられなくなる可能性があります。
こうした「内巻」の厳しい環境の中で、自動車業界内では「粗暴な価格競争は『手抜き工事、偽造品の販売』につながる」という警告が発されており、消費者の間でも「長期的な品質低下、アフターサービス悪化、イノベーション減少」のリスクへの懸念から、購入を延期する動きが見られ始めています。
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績