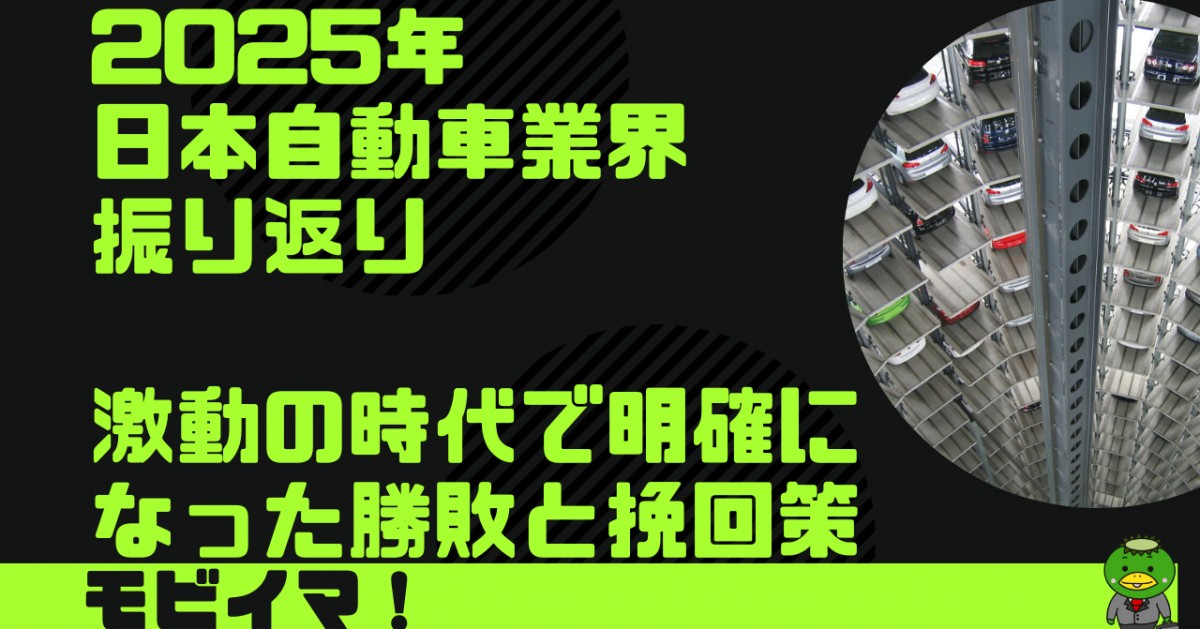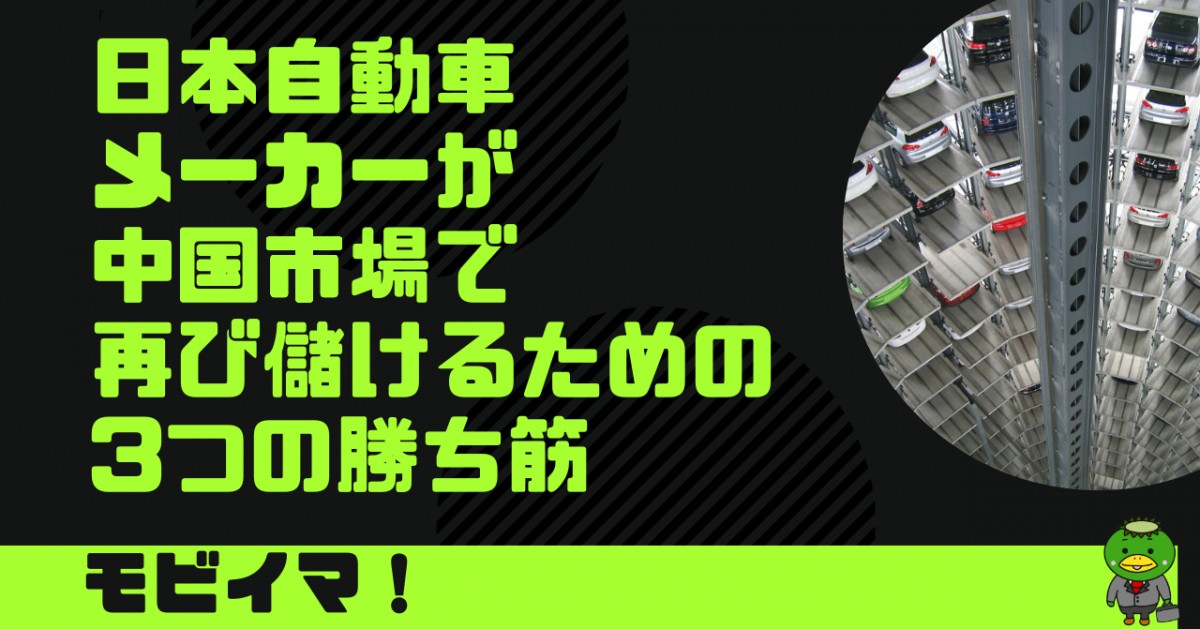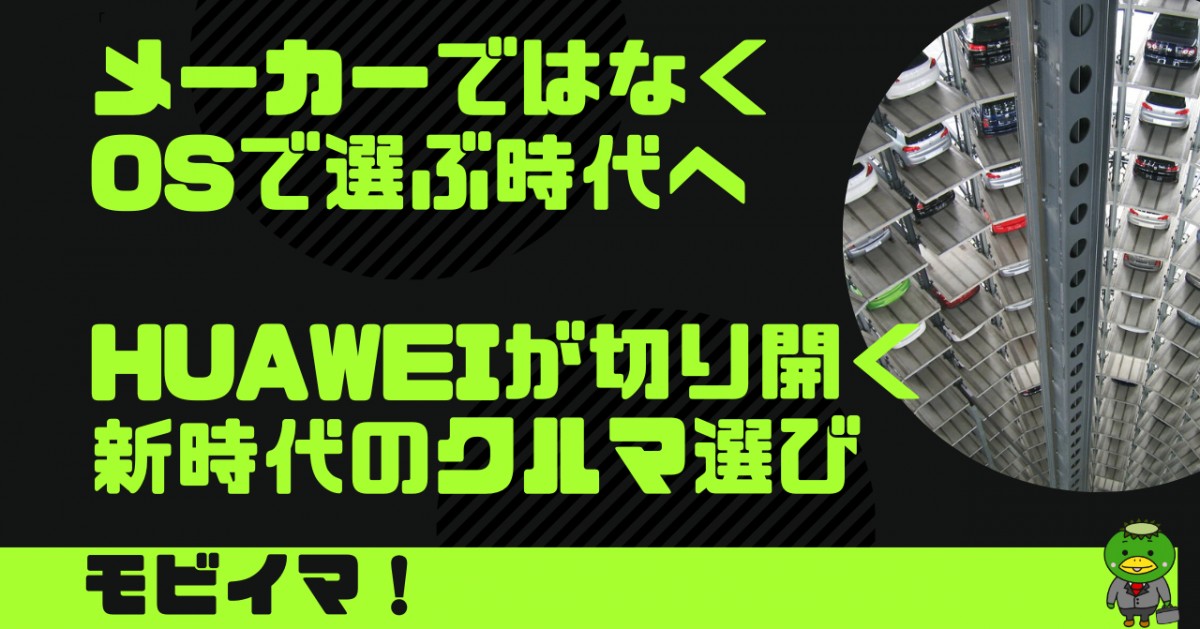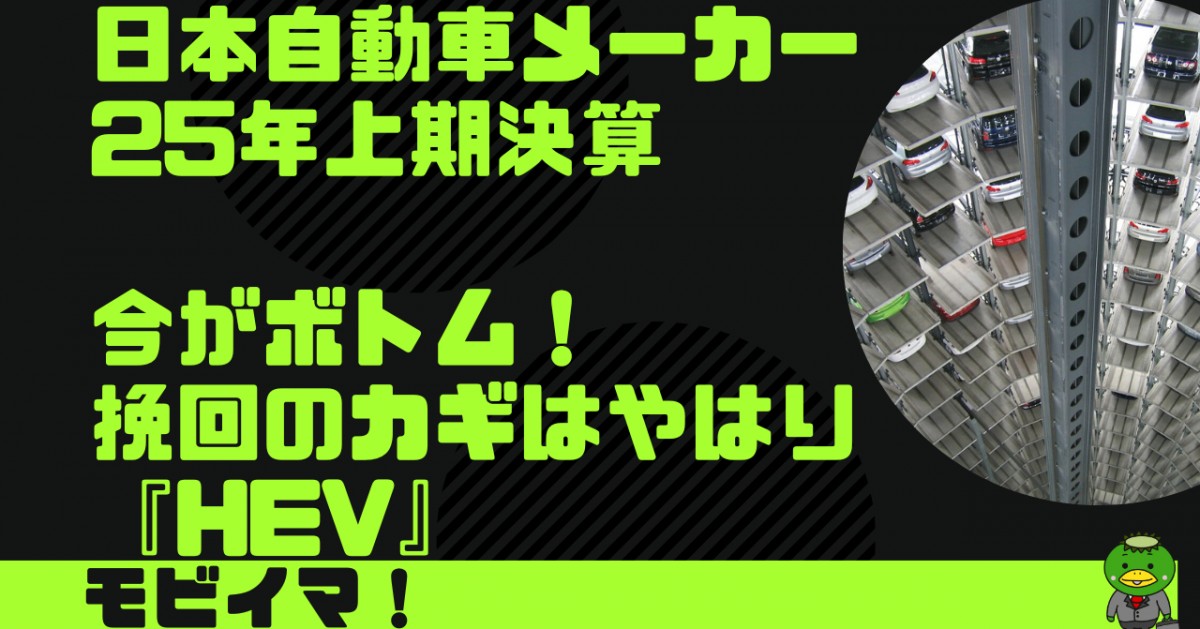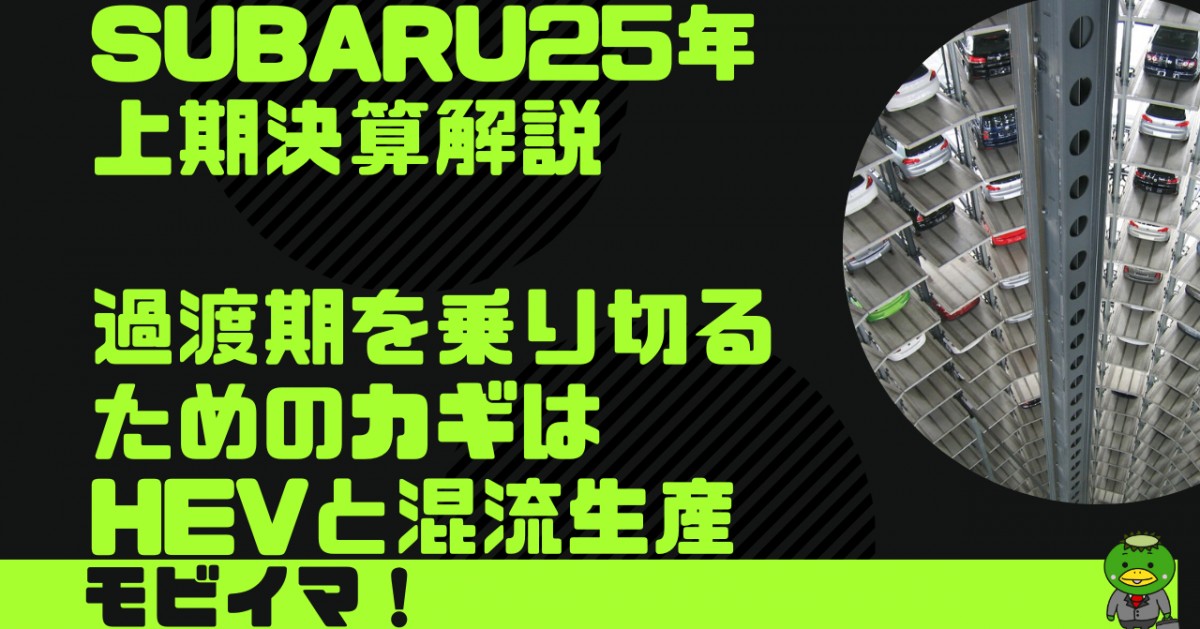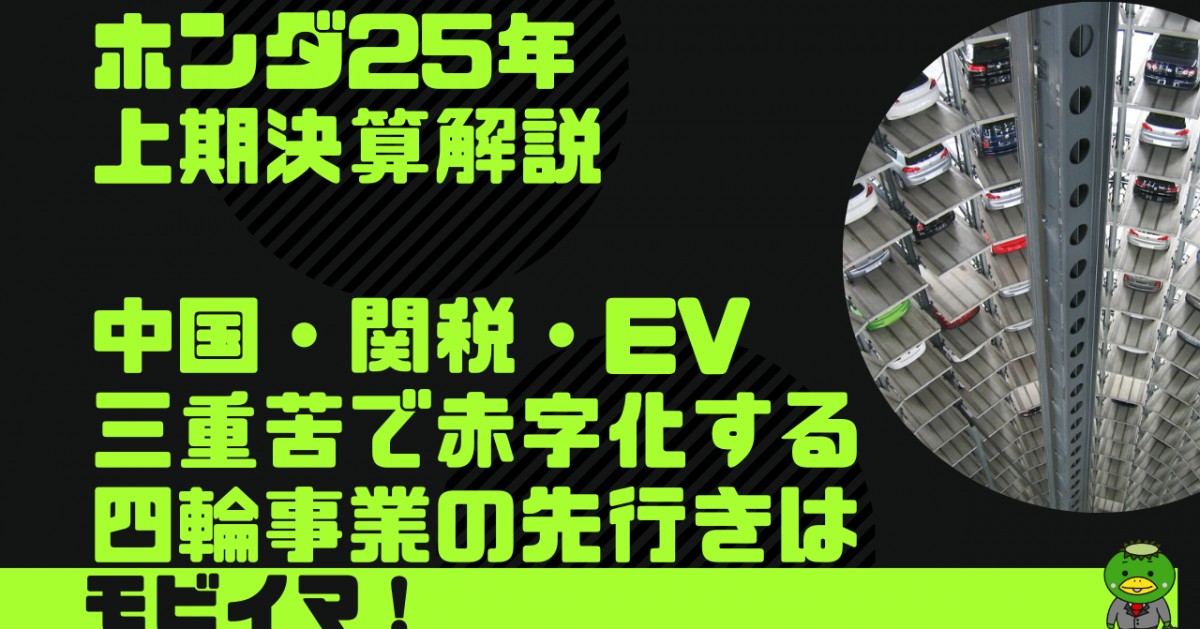今週のテーマは『サプライヤー』おすすめ本/レポ モビイマ!【Vol.4】
━━━━━━━━━━━━━━━━
クルマのイマがわかる「モビイマ!」
( 2021年6月17日発行 )
━━━━━━━━━━━━━━━━
ご安全に!
週2回配信に変更になり、木曜日朝7時配信初回のモビイマ!です。
気がつけばもう上半期が終わり…自動車業界はなんだかんだでものすごくばたばたした半年でした。そろそろ落ち着いてくれないかなと思うものの、一向にその気配はありません。
下期は多少なりとも落ち着くといいなぁ(ずっと言っている)
今回のテーマは『サプライヤー』です。
ちょっとニュースレターのタイトルのつけ方も変えてみました。こちらの方が内容がわかるかな。。。
【目次】
1. Mobility Insight Report
-
曙ブレーキ検査不正特別調査委員会報告書
2.クルマ・マメチシキ
-
「Tier○」
3.カッパッパの今週の1冊
-
モビリティーサプライヤー進化論 CASE時代を勝ち抜くのは誰か
1. Mobility Insight Report

Mobility Insights Reportでは、Web上で無料で読むことのできる自動車関連のおすすめレポートを紹介します。ニュースより一歩踏み込んだ情報に触れることで、周りと一歩差がつく。
これであなたも自動車通!
曙ブレーキ検査不正特別調査委員会報告書
みなさんは第3者委員会(特別調査会)の報告書を読んだことがあるでしょうか。企業においてコンプライアンス上の問題が生じた際に、信頼を取り戻すため第三者である専門家に調査し、被害拡大防止のための措置を講じたり、再発防止策の策定が記された報告書です。
この報告書、部外者から見てもわかるように書かれているので、知らない分野でも読めば原因が理解できる、また自分にかかわる分野だと、「あぁーわかるわかる」と実務に近い実例が出てくるので非常に面白いです。
ブレーキメーカーの曙ブレーキが検査不正で出した特別調査委員会報告書は自動車部品メーカーがいかに受注、品質保証業務を行い、そしてどのような不正が行われ、何が問題だったのか。部品メーカーの業務がわかる大変良い資料になっています。
ただいかんせん誰でもわかるように書かれているのでとても長い…
ということで今回は読むべきポイントをかいつまんで紹介します。
ポイント①:製品開発・生産過程の概要(6ページ)

ここでは製品の受注から納入までのフローが書かれています。短くはありますが、自動車部品メーカーの業務の流れがまとまっていてわかりやすいですね。
ポイント②:不正の具体的な内容(8ページ)

今回の不正の具体的な内容です。検査することが出荷の前提なのに、検査自体が行われていなかった、修正されていた。これはあかん!(と思う一方で実務だと…と思われる方もいるのではないでしょうか)
ポイント③:背景・原因(9ページ)


報告書の一番読み応えのある部分。なぜ不正は起きてしまったのか。
内部けん制、コンプライアンス意識の欠如、検証不足。そんなのもできてないの?と思われるかもしれませんが、実務をやっている人間だとわかるよなぁとうなづける部分でもあります。

なお今回の件に関していえば、製品のスペック上は客先の規格を満たすものであり問題はありませんでした。しかし、実施すると申請していた検査で不正を起こしていたことは、実際の製品が本当に十分な機能を持ったものなのか保証ができない、極めて大きな問題です。
ポイント④:本件不適切行為に対する再発防止策について

不正に対しての対策案。実務の人だと、実際はどんな対策書を書いたのかなと気になるとこを。実際に効果があるのだろうかや機能するのかなという視点で見ると楽しいです(第3者委員会レベルになると、対策は割としっかりしています)
今回は少し変わったレポートを紹介しましたが、自動車関連に勤められている方には非常に身近で面白く感じられる(もしくは辛い)、勤めていない方でも実際の業務がわかり参考になったのではないでしょうか。
不正を起こした企業で出てくる第3者委員会報告書、なかなか興味深いので関係ない分野でも読んでみることお勧めします。(最近だと水虫の薬異剤混入で問題になった小林化工の報告書が面白かったです)
2.クルマ・マメチシキ

このコーナーでは知っておきたい自動車業界用語や明日人にしゃべりたくなるクルマに関わる豆知識を紹介します。
雑談のネタにぜひご活用を!
【Tier〇】
自動車業界ではサプライヤーの階層を指す言葉。Tier1=一次仕入れ先、Tier2=二次仕入れ先。Tier1は比較的大企業であることが多いが、階層を経るに従い、企業規模が小さくなる傾向にある。ただ1つの部品が欠けると、自動車はつくることができることが出来なくなるので、末端までサプライチェーンを把握しておくことが重要。
「ケイレツ」が基本となる日本自動車業界では完成車メーカーを頂点としたサプライチェーンが構築されていることが多いが、欧州などではボッシュ、コンチネンタルといったメガサプライヤーが完成車メーカーよりも開発力を持っていることもある。
なお、Tier1のサプライヤーは完成車メーカーと下請け法で守られたTier2以降の仕入れ先との板挟みになることがよくある。
辛い(個人の感想です)
3.カッパッパの今週の1冊

自動車関連や仕事術、自己啓発本などをカッパッパの独断と偏見で紹介します。
面白そうだなと思ったら、ぜひ読んでください。

「CASE」という技術トレンドが、自動車業界の変革を加速している。その影響は自動車メーカーだけでなく、サプライヤーにも及ぶ。本書では日系サプライヤーへのCASEの影響を包括的に捉えて今後の経営課題を探りつつ、異業種プレーヤーのあるべき取り組みも含めて、大変革時代を勝ち抜くための方策を提示する。
技術革新、CASEによる自動車サプライヤー立ち位置の変化、現状把握と生き残るためにどのような戦略をマクロな視点で書いた良書。CASEについて書かれた本はたくさんあるが、自動車部品メーカーに焦点を当てた本は少なく、この本は体系的によくまとまっており、部品メーカー勤めの方、就職活動で受験される方はぜひとも読んでおいた方が良い。
なお、題名と著者名から海外の本の翻訳なのかと思ってしまうのだが、中身は100%日本の話。
本書は4部構成で、サプライヤーの進化の在り方を論じている。第1部では、CASEの動向やグローバルサプライチェーン構造の変化を踏まえて、サプライヤーへの影響と採るべき施策の方向性を考察した。第2部では、採るべき施策の具体的な取り組みの在り方を、先行企業の事例も交えながら示した。第3部では、自動車産業以外の事業者にとっての自動車業界の大変革を捉えた取り組み方向性を示しており、情報通信事業者や素材事業者、インフラ事業者、電機事業者、金融事業者を取り上げて考察した。最後に第4部として、各産業のキーパーソンや行政との対話を通じて、サプライヤーの進化の方向性や具体的な取り組みの在り方を確認しつつ、各社の取り組み事例を紹介
特に読むべきなのは【第1部】事業環境の変化と勝ち残りのための処方箋と【第2部】勝ち残りのための7つの実践的アプローチ。「ケイレツ」という日本独特の自動車業界のサプライチェーンの強み、欧州との比較をしたうえで、電動化やITの進展により、どのようにこれから変わるのかが示されています。各部品ごとに分析していることも特徴的で、部品に応じた戦略をとるように指南。
読んでいて「ははーん、なるほど」とうなづけるところが非常に多く、特に欧州メーカーとの比較が読んで非常に参考になりました。既存日本部品メーカーは欧州メガサプライヤーに比べ、動きが遅く、積極的な変革ができていないと感じる一方、新規参入の日本電産などが売り込みに貪欲であることを考えると10年後の部品メーカーはプレイヤーが変わっているのかもしれないなぁと。
「ケイレツ」は確かにこれまで日本自動車業界を支え、進歩させてきた要因の一つではあるのですが、加速する時代変化のスピード、「すり合わせ」技術がMBD/プラットフォーム共通化により不要になる可能性を考えると、現状のまま維持し続けることは難しいかもしれません。
ただ水平分業型になれば、売り込みのチャンスも生まれるわけで、これまで完成車メーカーから指示され、その要望にいかに応えるかに注力してきた部品メーカーが提案型の売り込みを行っていけば新しいビジネスチャンスにつながります。保守的、典型的な日本型企業である「ケイレツ」部品メーカーがチャレンジできるか。経営手腕が問われそうです。
完成車メーカー以上に淘汰が進むであろう自動車部品メーカー。関係者の人はぜひとも抑えていきたい1冊。お勤めの方は本書と自分の会社の中長期計画を比べて、どのような立ち位置、戦略で生き残ろうとしているのか、比較することをお勧めします。
【週の半ばの独り言】
3月ごろに出た赤城乳業の「かじるバターアイス」がとても好きで、めっちゃ探していたのですがすでに販売休止になっていることを知りました。悲しい。再販してほしい。
みなさんのおすすめアイスがあればTwitterで教えてください。
こちらニュースレター、特別企画も計画中です。皆さんの関心の高い内容になる思うので乞うご期待。
最後までお読みいただきありがとうございます!!
クルマのイマがわかる「モビイマ!」
感想をいただけると大変うれしいです。
Twitterボタンで感想、つぶやいてもらえると励みになります!
さあ、今週も残り2日‼やっていきましょう‼
・CASEなどの業界トレンドを詳細に解説
・各自動車メーカーの戦略や決算分析
すでに登録済みの方は こちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績