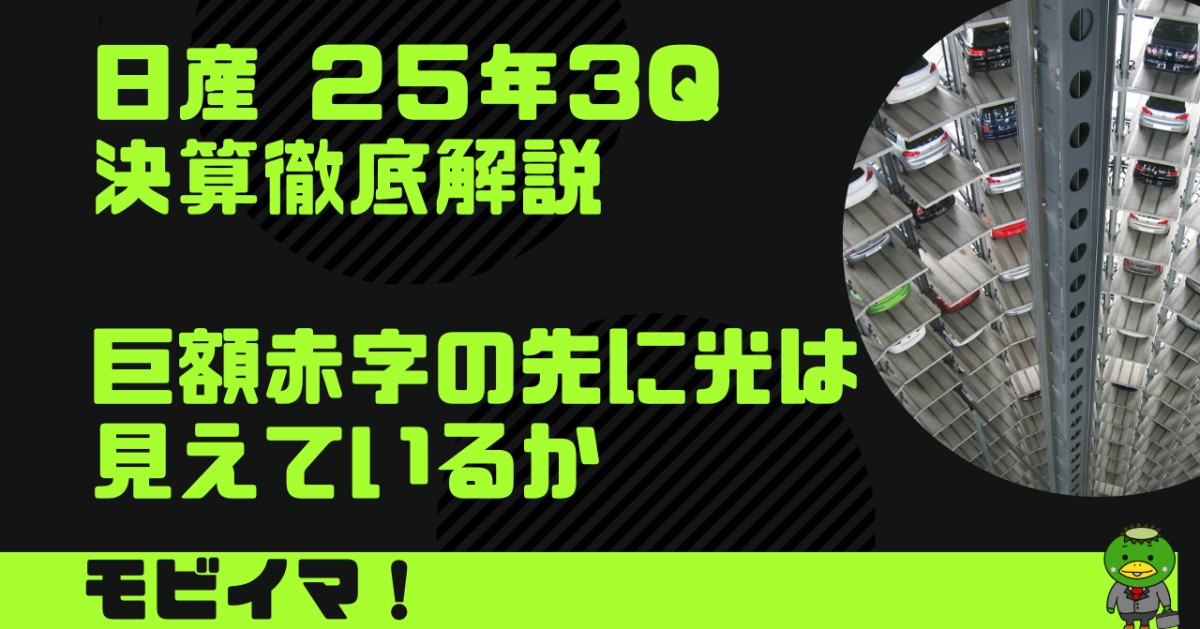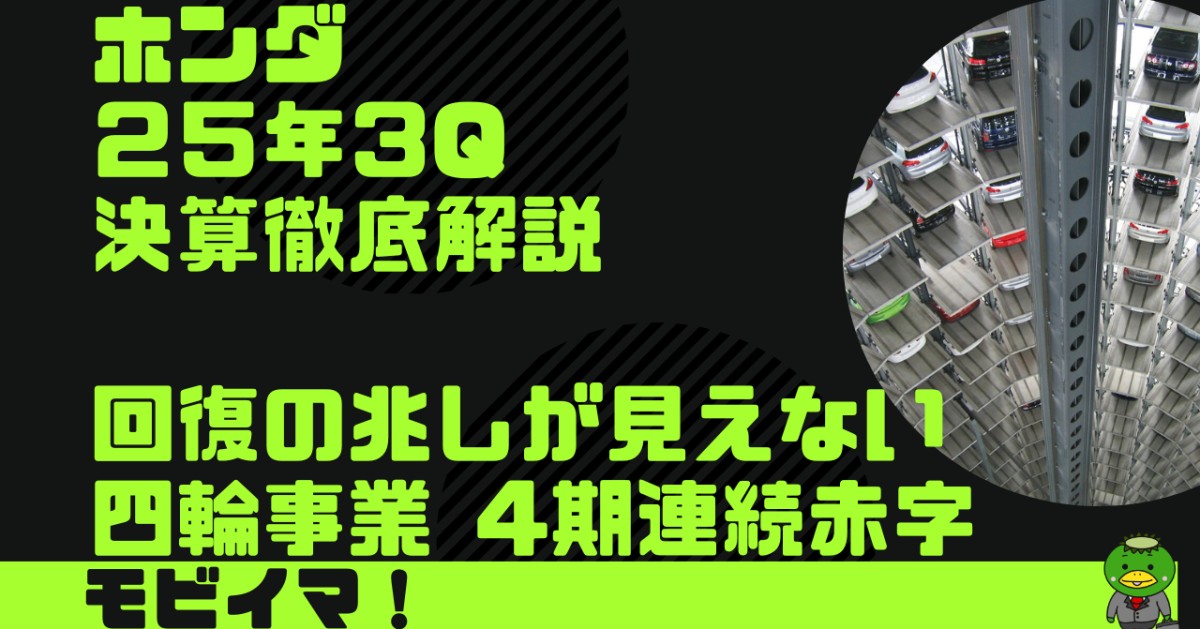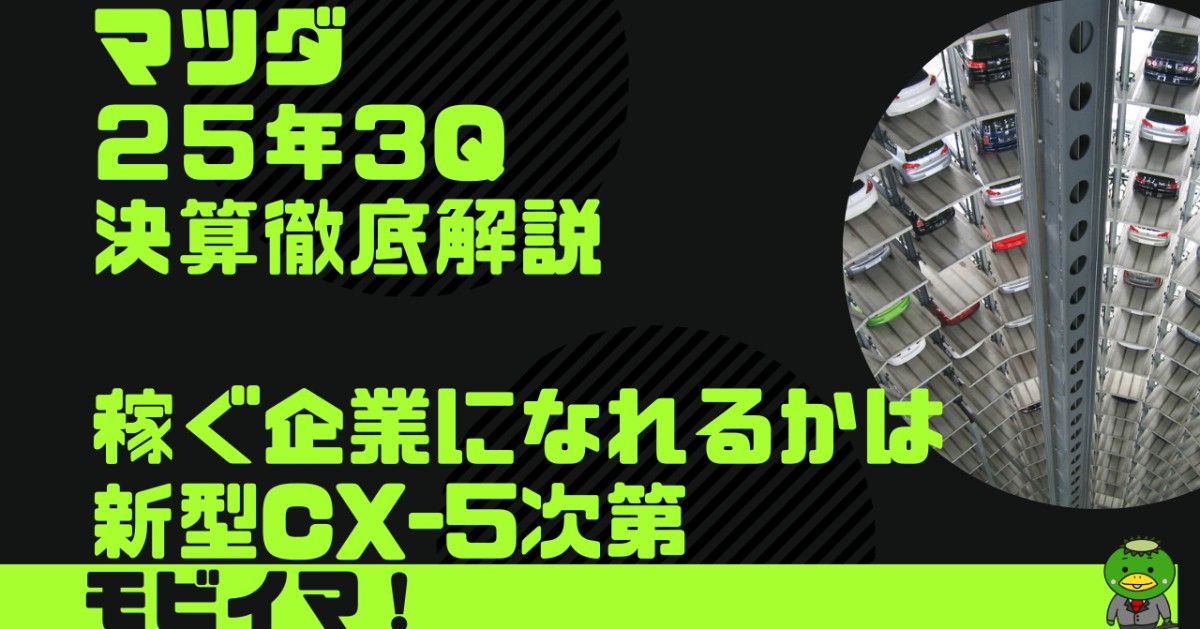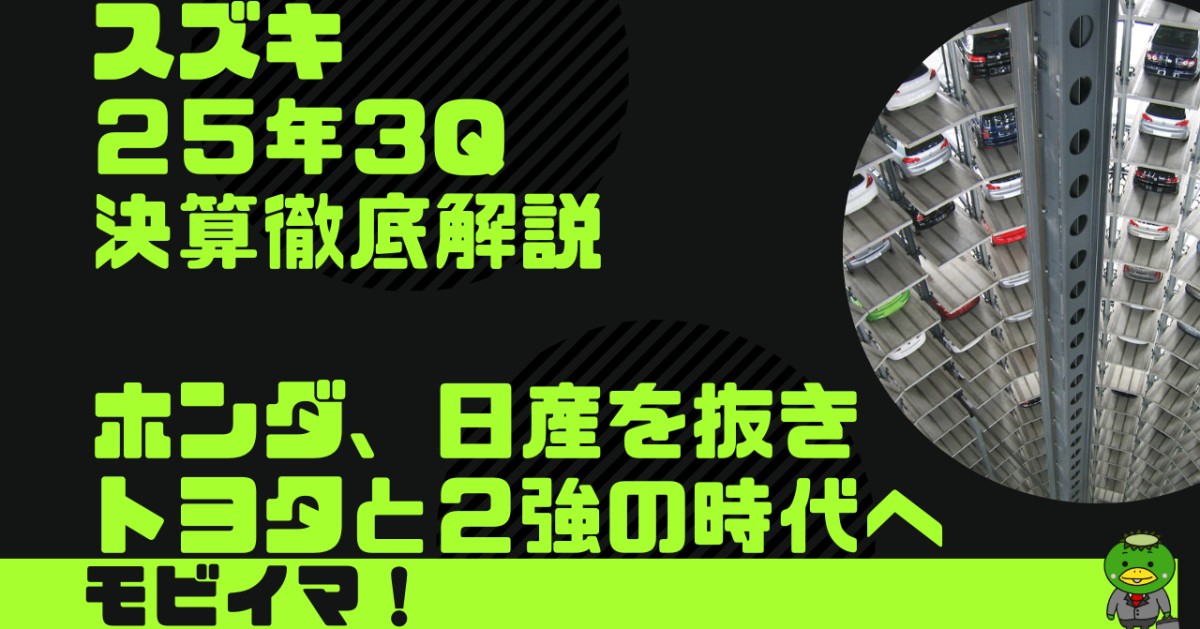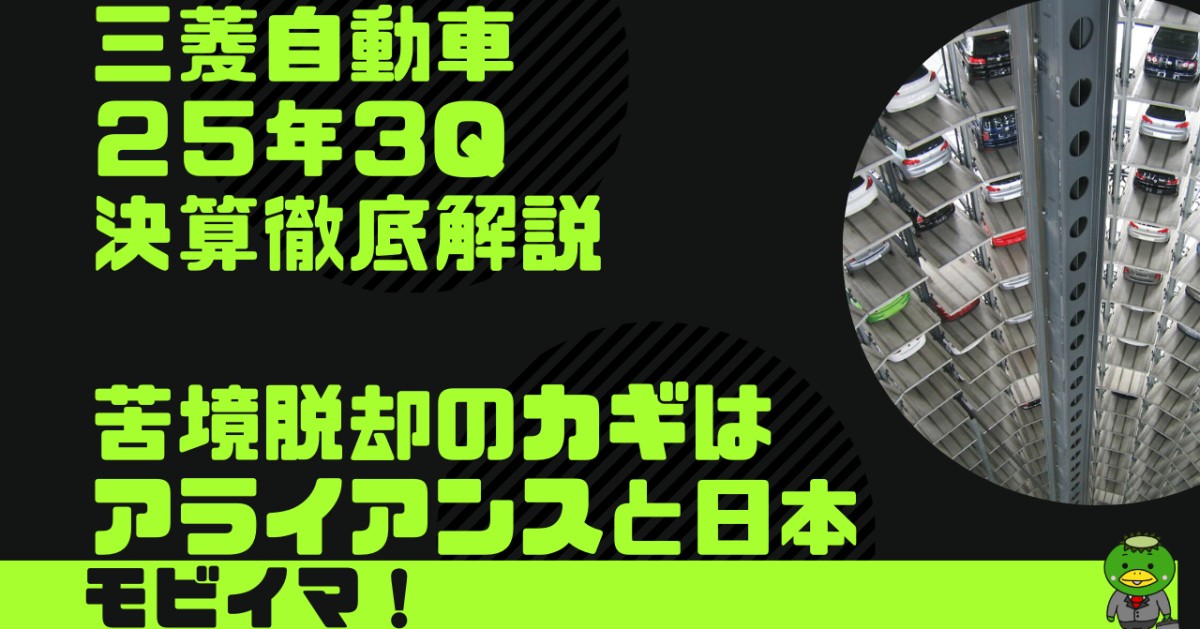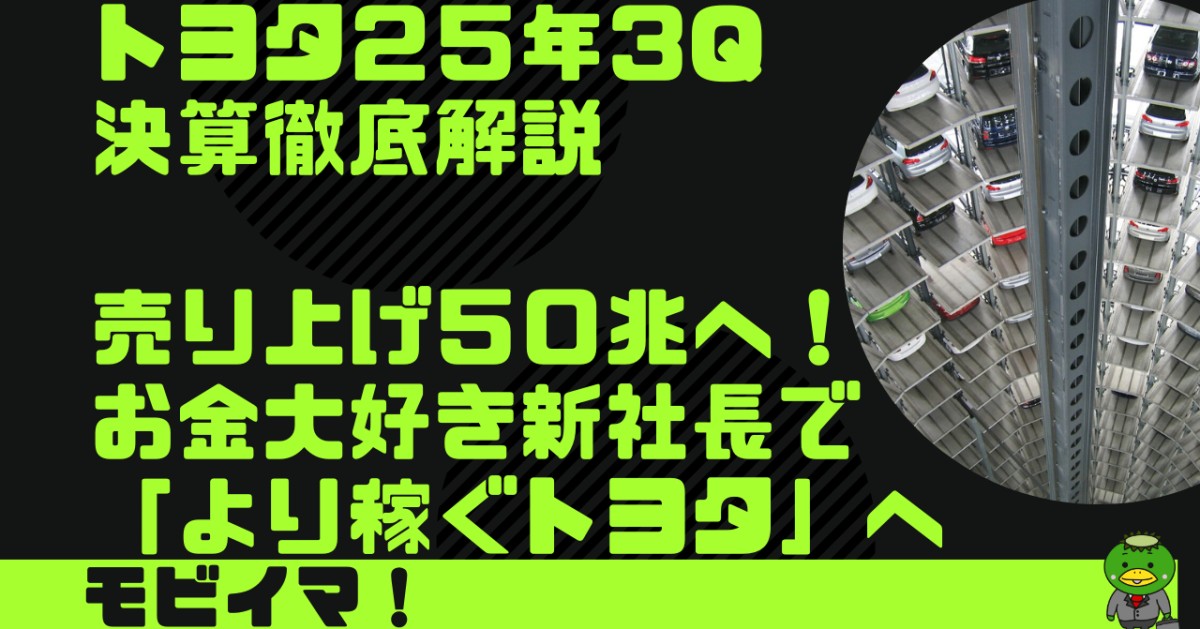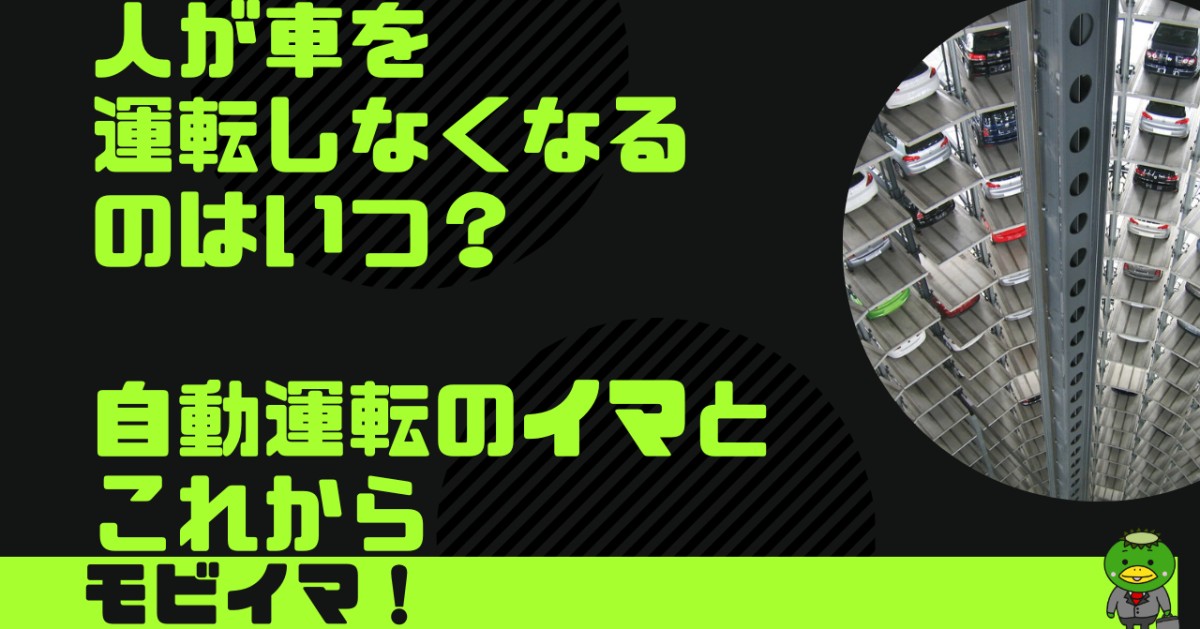【池田直渡氏対談②】テスラの強みが弱みに変わるとき
ご安全に!
コンビニで買うアイスが美味しい季節になってうれしいカッパッパです。
今回は前回に引き続き、池田直渡氏(@naotoikeda)との対談をお送りします。
今回は皆さんが一番気になるであろうテスラが今後どうなるのか。絶好調テスラがやがて直面する困難、「強みが弱みに変わる」とはどういうことか。とても充実した、ここでしか読めない対談。それでは早速続きをどうぞ。
1.モビトーク

好調テスラのアキレス腱
カッパ:
池田さんの見解として現実的なライン、テスラの2025年、30年どれぐらいが妥当な台数だと思いますか?
池田:
例えば、企業成長の危険ラインの前例として見るのは、トヨタ。1999年から2008年までに、10%成長を8年ぐらい続けたじゃないすか。
カッパ:
2000年代前半ですね、わかります。
池田:
その成長でもリーマンショック時、トヨタは前年2兆円の黒字から4600億円の赤字に沈んだんですよ。だから、石橋をたたいて渡るトヨタですら、10%成長を10年続けるのは相当無理だったってことですよね。そのぐらいが限界じゃないですか、普通に考えて。
カッパ:
ボリュームラインとしては、ギガベルリンとテキサスが立ち上がれば150万台は確実。上海が能増すれば多分200万台のレベルはいけるだろう。中国は多分これからまだ伸びるので工場を1個追加で作ったとして、200万台後半ぐらいまでは、2025年ぐらいまでとかでいけるのかなと。ただそこからは今のままだと、ちょっと難しいかなとは思ったりしますね。
池田:
そもそも今、テスラがなぜ快進撃をしてるかっていう理由を考えて見ましょう。まず一番でかいのは、常に需要が供給を上回ってるからですよ。つまり、販売店や宣伝がいらないとかも含め、販売に関して施策を打つ必要が一切なくて、作りさえすれば必ず売れてしまう。その形に持ってきた。それはスゴいことです。
コマーシャルもやらなくても売れる。販売店がないから営業も要らない。お客さんが勝手にポチって買ってくれる。そういうやり方で、常に販売が生産キャパシティを上回ってる。工場は常に100%フル稼働、休日の稼働まで入れると100%オーバーです。製造業の方なら、この状態だったら利益率めちゃくちゃ上がるのはわかると思います。
だから、20%の利益率。けど、それは逆に言うと要注意だよねってボクは見るわけですよ。
カッパ:
20%の利益率があるというのは、裏返せば、罠にはまる原因になる?
池田:
テスラはまだ、自分たちの供給できる量が需要を上回るフェーズに入ったことがないんですよ。普通の自動車メーカーは、成り行きで売れる量以上に、どうやって売るかが日常的な経営課題。要するに自分たちのポテンシャル上限に達した後で、これ以上どうやって売っていくかっていうことが事業課題なんです。だからまだテスラは、現状で事業課題に当たってないんですよ。
カッパ:
なるほど、そうですね。
池田:
今は100を超える生産稼働率が例えば、90ぐらいになりました。90なったときに、利益率どうなるんだと。テスラの工場の設計がどうなってるか。非常に危険なのが、受注残を減らすための最速ラインを設計していた場合。生産量を減らしたらすごい利益率が落っこちるラインができてる可能性が高いんですよ。それが2000年代前半のトヨタが落ちた罠ですよ、まさに。
カッパ:
この前僕も記事書いたんすけどテスラが今儲かってるのって稼働率がすごい高いので、設備償却の固定費が分散されているから。それをわかる方って少ないですよね。
2009年のトヨタ、リーマンショックで赤字に転落。あのあとトヨタは全部工場新規立ち上げを止めたっていう失敗、すごい苦い経験がある。供給>需要になるのがいつなのか、その時にどうコントロールするのかながテスラの今後の課題ですよね。
池田:
トヨタは「意思のある踊り場」として工場の新規投資を一旦全部止めました。そして体質改善のために、旧来の工場のロットをすべて小さくしていく、ロット生産に対応できるように工場全部改良した。逆に言えば、失敗が今のTNGAを産んでる。
今のテスラの一番のアキレス腱は、100パー以上でぶん回しているキャパです。しかもまだ足りないので工場をどんどん作ってる。当然、いつかは、需要を供給が上回ります。標準的な自動車工場のキャパは年間25万台。テスラはそれが大型で、50万台、100万台の工場をボンボン立てちゃってる。増産が追いつかないから大型工場が欲しいんですが、いつか供給が需要を上回る。その時、いきなり稼働率が落っこったら、そんなでかいキャパの工場ってどうなるのか。25万台の工場よりリスクが大きい可能性が高い。なんか見ててすごく怖いんですよね、その辺りの経営が。
テスラ高需要はどこまで続くか
カッパ:
この問題、テスラの潜在的な需要がどこまであるのかが重要だと思うんですが、池田さんはどれあたりにあると思いますか?今の価格帯だとモデル3で500万円台。このボリュームゾーンが果たしてどれくらいあるのか。
池田:
そこは伸び縮みすると思ってるんです。例えば昔、100万枚のCDが売れた歌手が今も再び100万枚売れるかという話。人気によって左右される。テスラは中身が優れているから売れているんだとされている。ただ、一般的に自由経済界における商品事業というのは、一定のところから先はブームなんですよ。
そう考えると人気は常に水物で変化するものだと捉えておかなきゃいけないし、だからこそ、工場の生産キャパシティはスケーラブルであることってすごい重要なんですよ。なぜなら水物を相手にするんだから。
テスラの強みが弱みに変わるとき
池田:
工場の稼働率の問題以外に何があるかというと、工場が赤字にならない程度の稼働率で回した時、その生産キャパが需要を上回ると、在庫が積み上がっちゃうわけです。これは設備投資産業の宿命です。稼働率を下げたら、大出血で死んでしまう。だから止めるわけにはいかない。だったら売るしかないわけです。従来のメーカーだったらディーラーにハッパかけて売らせるわけですよ。けれどもテスラは販売店がないのでその手が取れない。
テスラは事業を動かすエンジンが需要1本なんですよ。そこに多様性がない。営業マンがお百度踏んで、頑張って値引きして、何だったらお誕生日に花束を持っていって何とか契約してもらう。そんな浪花節みたいなことをテスラはできないし、するつもりもない。本当はそんなことは誰だってしたくはないですが、工場を止められない以上仕方ない。ある種の禁じ手の領域として、生産量に合わせた販売っていう辻褄合わせをやらざるを得ないのです。その裏技的技術っていうのは自動車業界ってずっと積んできたわけですよ。
そういう、需給のギャップを調整する調整代として、販売店もあるし広告もあるし、場合によっては出版社とかタイアップとかもある。ありとあらゆる方法を使って今の自分たちの生産キャパの都合に合わせた需要を作り出すための仕掛けっていうのは、自動車業界は持ってるわけですよね。それを全部を「過去に縛られた愚かなレガシー技術である」というのは、調子が良い間は言えるんでしょうけど、ひとたび供給が需要を上回ったときに、出来ることはイーロン・マスクがtweetを増やすことと、値下げだけです。それ以外に調整手段を何一つ持ってなくて本当に大丈夫なんですか。これがテスラの経営を見ていて思うボクの正直な感想ですよ。
カッパ:
果たして供給>需要がどのタイミングで来るかですよね。
池田:
今見てると、もうモデルSが全然売れなくなってます。モデルXは元々台数が出るクルマじゃなくて、既にモデル3も落ち始めていて、モデルYに主力が移りつつある。ということは、モデルY一本足になりつつあるということです。
それって怖くないですか。宿命的に、商品は人気で売れ行きが変わる水物です。ただでさえ生産キャパシティを引き上げて、とにかく沢山作ろうとしている中で、売れ筋がどんどん1車種に集中してきてる。リスクは高まっています。
モデル2は無理やりでも出すべきだった?
池田:
だから僕は、テスラが安全にやっていこうと思ったら、実はモデル2を意地でも出すべきだったんじゃないかと思うんですよ。
カッパ:
モデル2出したら、絶対に利益率は下がりますよね?
池田:
間違いなく下がります。下がるけれども、安くなって、新規需要、今まで買えなかった客層に需要が広がれば、色んなことへの対応をせざるを得なくなります。今までのテスララブなファンに向けの「あばたもえくぼ」のビジネスはできなくなります。「こっちは金を払ってんだぞ」とナチュラルに思って入る客。それは世の中で言う普通の客なんですが、そういう面倒な人たちに対しての販売とサービスのバグ出しみたいな対応を否応なく100本ノックでやっていくしかなくなります。それをやることでテスラは強くなれるのではないかと思います。
カッパ:
今のテスラは一部を我慢して乗っているというか故障することも楽しいみたいな。
池田:
所有すること、乗ることを趣味と捉える人達ですよね。オフミとかに行くような人達です。
カッパ:
言うと怒られるかもしれないけど、昔のイタリア車とかアメ車みたいな感じですよね。
池田:
ある種の「美しいライフスタイル」を買っているのであって、クルマっていう実用消費財を買ってるわけじゃない。一方で、必要に迫られて消費財を買う人たちにしてみれば、金を払って不便を買うなんてもっての外なので、もうすごい些細なことが気に入らないわけですよ。
例えばチリが合ってるかどうかとか、塗装のムラがどうだとか、そういうところも気になるし、「値引きゼロってどういうことだ」とか「納車は届けに来るのが当然」みたいな、本当にくだらないトラブルが起きるわけですよ。それが大衆を相手にするビジネスです。多分今のテスラクラスターの人の価値観からすると、それは愚かだって言うんでしょうが、それで終われるんならいいけれども、販売台数が200万台を越えたら、好むと好まざるとに関わらず、買い手と売り手の関係の中でそういう旧来の文化が持ち込まれる。だからモデル2を出して、その壁に早く直面した方が良いんじゃないかなと。そこが変わらないとやがてボクは断末魔がやってくると思うんですよね。
カッパ:
言われる通りだと思います。今のモデルY価格は600万ぐらい。600万を買える人って、そこまでいない。絶対伸びないんですよね。モデル2ってなってきたときに、売り上げは伸びるかもしれないけど利益率落ちていく。さっき言われたような工場の稼働供給状況なり、供給>需要っていう状況も出てくると。 そうなってきたときにテスラがどうなっていくのか。まだちょっと先かとは思いますけど、今のままの成長を維持できるかはかなり怪しいですね。
大衆化する難しさ
池田:
大衆化することの難しさには前例がたくさんあって、例えばとある輸入車ディーラーは海外の高級メーカーだけ扱っていて、お客さんはディーラーの言う通り修理なり整備なりを受けてくれた。ところが海外の大衆ブランドを扱い始めたら客層が変わっちゃった。 もうタイヤにスリップサインが出てるようなのを、「まだ乗れる」と言って交換させてくれないと。彼らもその常識の違いに驚いたんです。お客さんってこんなに違うんだって。そこから今度は、客層に合わせることでディーラーのレベルが落っこってっちゃった。「正論言っても聞いてくれないなら、言いなりにやろう」と。だからそこはもう、断絶があるんですね、お客さんの。違うクラスのクルマを扱うためには、違う種類の従業員じゃないと回せない。
ディーラーもレベルダウンしてしまって、最終的には高級ブランドを扱うブランドイメージにそぐわない人材になってきちゃったと。そのぐらい変わらないとつまり大衆向けの商品というのは扱えないんだっていうことなんですよね。
カッパ:
今、テスラを買っている方は、アーリーアダプターですよねあくまでも。これから台数を出していくためにはマジョリティーのところに絶対入っていかないといけない。それが今のテスラではおそらくまだ無理そうですね。
今テスラを推される方っていうのは、リテラシーの高い方が多い。階層が高い方でマジョリティーの人たちっていうのが実際どんな方なのかっていうのがあまり見えてないんじゃないかなあというところは、思ったりします。
第2回はここまで。自分で言うのもなんですが、ここでしか読めないすごく内容の濃いテスラ分析。テスラが立ち向かわなくてはいけない「供給>需要」の壁。それがいつになり、果たしてどう乗り越えるのか。
次回はテスラの更なるリスクとこれからのまとめ。こちらも非常に充実した対談内容になっています。本当に乞うご期待!
・CASEなどの業界トレンドを詳細に解説
・各自動車メーカーの戦略や決算分析
すでに登録済みの方は こちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績